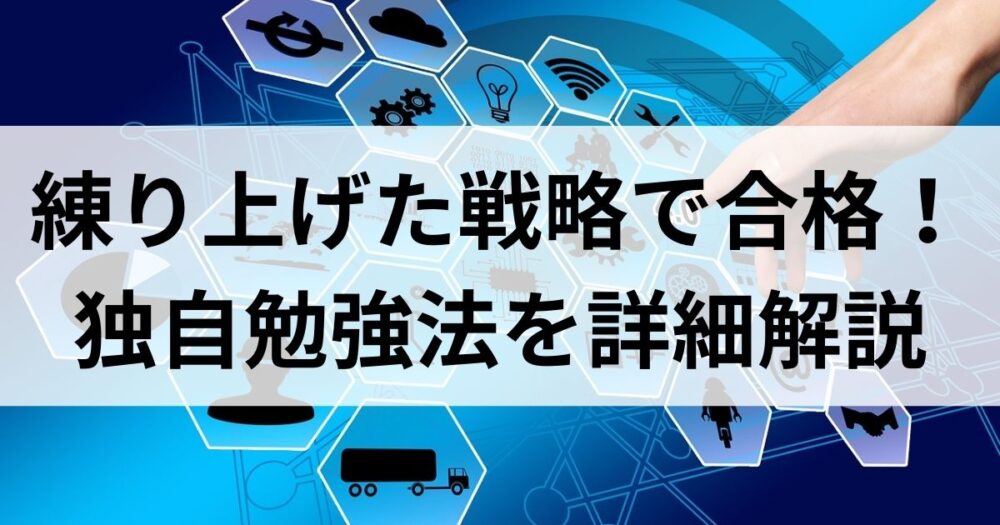
行政書士試験に合格するには半年~1年の勉強が必要です。
勉強時間に直すと500~1000時間です。
1000時間を1年かけて勉強するとしたら、
1日3時間は勉強しなければいけません。
「残業続きなのに3時間も毎日勉強できるか」
仕事は早くても20時上がり。
遅いときは日をまたぐこともありました。
1日3時間も時間を作ることなんてできない状況です。
働きながら行政書士試験に合格するなんて無理だと思っていました。
ただ、受験を諦めようとは思いませんでした。
行政書士になって人生を変えたいと、
強く強く思っていたからです。
ネットには働きながらでも合格したという人がいます。
自分が無理だと思っているだけで、
実際は働きながらでも行政書士試験に、
合格できるカラクリが何かあるに違いない、
と信じて疑いませんでした。
働きながら合格するには、
効率を求めないといけません。
行政書士試験は膨大な勉強時間が必要だから、
働きながら合格するのは無理なのではありません。
効率を求めずに勉強するから無理だといわれるのです。
- 行政書士試験に働きながら合格するのは無理と言われる5つの理由
- 働きながら合格を目指すのは無理ではない|効率の良い戦略を練る
- 働きながら行政書士試験に合格するために必要な7つの要素
- 1.なぜ行政書士試験を受けるのか目的を明確にする。
- 2.試験制度を確認し本試験までの工程を理解する。
- 3.試験の出題範囲を分析して傾向をつかむ。
- 4.時期に応じてどんな勉強をするか考える。
- 5.教材を絞り学習効果の高い勉強スケジュールを組む。
- 6.勉強の記録を付け教材を適切な時期に使う。
- 7.本試験前日・当日の動きを確認する。
- 行政書士試験に合格するためには練りに練った勉強法が必須
行政書士試験に働きながら合格するのは無理と言われる5つの理由
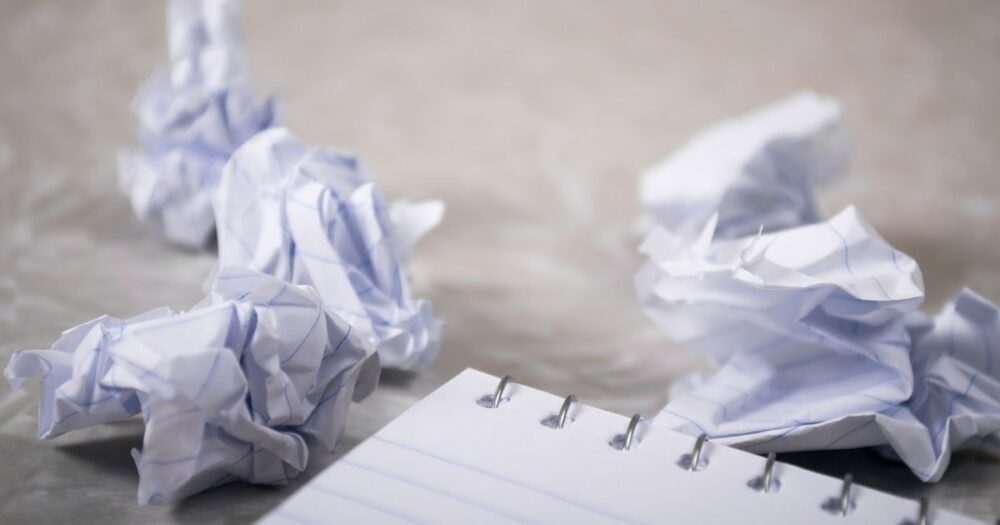
行政書士試験の話になると必ず2つの意見に分かれます。
「行政書士試験に働きながら合格するなんて無理」
「行政書士試験は働きながらでも合格できる」
どっちが正解なんだろうかと思います。
私は働きながら合格したので、
働きながら合格することはできます。
ただ、働きながらでは無理と言われる理由が5つあります。
■合格率10%の試験に働きながら受かるわけがない
■法学部出身でも落ちるのだから合格は無理
■勉強をしている目的を見失いやすい
■勉強時間の確保ができず挫折する
■モチベーションが下がりやすい
合格率10%の試験に働きながら受かるわけがない
行政書士試験は合格率が10%の試験です。
10人受けて9人が不合格になるんです。
非常に厳しい試験だということがわかります。
合格率も低い試験なのに、
働きながら合格するなんて、
片手間で勉強するのと一緒だと思う人もいます。
だから、働きながらの受験に否定的になるんです。
ただ、受験生全体の合格率が10%であって、
あなたの合格率とは全く関係がありません。
行政書士試験は誰でも受験できるので、
記念受験をする人だっているのです。
本気で受験している人は全体の30%ぐらいです。
合格率10%だからといって、ひるむ必要はありません。
法学部出身でも落ちるのだから働きながらの合格は無理
行政書士試験は法学部出身であっても、
準備をしないと不合格になってしまう試験です。
私の友人にも何人も不合格になった人がいます。
法学部出身の人が不合格になるのだから、
行政書士に働きながら合格するのは無理だ、
と思うのですが、この理由は簡単に否定できます。
理学部出身の私が合格できたので、
大学の出身学部では左右されません。
法律を知らなくても勉強法さえ知っていれば、
行政書士試験に合格することはできるんです。
諦める必要は一切ありません。
働きながらの勉強は目的を見失いやすい
残業続きの仕事は嫌だ、行政書士になって人生を変える!
一大決心をして行政書士試験の勉強を始めても、
毎日の家と職場の往復をしているうちに、
行政書士になるという決心が薄れていきます。
仕事をこなせば給料がもらえる。
今頑張らなくても不自由な暮らしにはならない。
1年間頑張るよりも目先のことに集中した方が楽。
行政書士になる必要はないんじゃないか。
日々の生活を送っていると仕事優先になり、
自分で決心したことを忘れていきます。
1年を振り返ったときに、
現状の不満を解消するためにも、
やっぱり勉強しておけばよかった、
と後悔することになります。
生活に不自由がないときに勉強することが、
一番良いのにもかかわらず、現状に満足して、
勉強する目的を忘れてしまいやすいのです。
勉強時間の確保ができず挫折する
働きながら勉強をするのは大変です。
今まで遊びに使っていた時間を、
勉強に当てるようになるので、
休みたいと思うようになります。
残業続きならなおさら、
家に帰ったら休みたいと思うはずです。
仕事で疲れたから少し休憩、
と思ってボーっとしていたら、
1時間経っていたということもありえます。
勉強しようと思っても時間が作れず、
挫折することになるのです。
働きながら無理なく合格を目指すには、
空き時間を活用した勉強が欠かせません。
数分でも良いので勉強することが大切です。
≫数分の勉強で効果があるのかと思う人には、この記事をおすすめします。
モチベーションが下がりやすい
働きながらの勉強はモチベーションが下がりやすくなります。
誰かに強制されたわけではないので、
勉強しなくてもペナルティはありません。
今のまま働いていても給料は支払われるので、
無理して勉強を続ける必要性がないのです。
人生を変えるために行政書士になるんだ、
と思って勉強を始めたとしても、
モチベーションが続かないのです。
1年間勉強するためには、
モチベーション維持も大切な要因になります。
働きながら合格を目指すのは無理ではない|効率の良い戦略を練る

働きながら行政書士試験合格を目指すのは難しいです。
しかし、働いても合格できる方法があります。
行政書士試験のことを知り、対策を練り、
効率の良い勉強法を実践できればいいのです。
私も残業サラリーマンをしながら、
限られた時間の中で合格しました。
学校の勉強もろくにせず、遊んでばかりで、
先生に職員室に呼び出される学校生活を送り、
大学では留年も経験しているのにも関わらずです。
私にできて、あなたにできないわけがありません。
働きながら無理なく合格するためには、
必要な要素を見極め、勉強に取り入れる必要があります。
働きながら行政書士試験に合格するために必要な7つの要素

働きながら行政書士試験に合格するには7つの要素が必要です。
1.なぜ行政書士試験を受けるのか目的を明確にする。
2.試験制度を確認し本試験までの工程を理解する。
3.試験の出題範囲を分析して傾向をつかむ。
4.時期に応じてどんな勉強をするか考える。
5.教材を絞り学習効果の高い勉強スケジュールを組む。
6.勉強の記録を付け教材を適切な時期に使う。
7.本試験前日・当日の動きを確認する。
1.なぜ行政書士試験を受けるのか目的を明確にする。
行政書士の勉強で挫折しない方法は初心を忘れない事です。
私は、仕事を言い訳に、
人生が小さくなっていくことに嫌気を感じて、
行政書士に望みをかけて挑みました。
私は目に見えるところに、
「ずっと○○で働き続けますか?」
と張り紙をして、目に入るたびに
「このままで良いわけがない。勉強をやるぞ!」
と自分を奮い立たせていました。
人の想いは、とても弱く小さなものです。
この瞬間に決意しても明日には忘れます。
しかし、
毎日初心を忘れなければ、
嫌でも勉強する気になります。
行政書士試験に合格しなければ人生が変わりません。
行政書士を目指そうと思った最初の想いは、
そのまま勉強の原動力になります。
あなたが、行政書士を目指す理由を、
紙に書いて忘れないようにしましょう。
モチベーションを保つ方法をいくつも持って勉強を継続する
ただ初心を思い出すだけでは、
気持ちが切り替わらないときがあります。
ここはテクニックで乗り切るんです。
運動をしたり、
部屋の片づけをしたり、
好きな音楽を聞いてから勉強したり、
いつもと違うところで勉強したりすることで、
モチベーションを維持することができます。
いくつも気分転換の方法を実践し、
行政書士の勉強を継続させましょう。
≫モチベーションはコントロールできます。いつまでも感情に振り回されるのはやめにしましょう
2.試験制度を確認し本試験までの工程を理解する。
無理なく働きながら合格するために、
本試験日、受験申込期間、合格基準は最低限知っておきましょう。
本試験日は11月第2日曜日です。
行政書士試験に合格するには、
11月に向けて勉強する必要があります。
受験申込期間は7月下旬~8月下旬です。
申込みを忘れると本試験を受けられません。
合格基準は細かく設定されています。
ただ、押さえておくべきことは2つ。
試験全体で180点を取る。一般知識で24点取る。
この2つさえ守れば合格基準はクリアできます。
3.試験の出題範囲を分析して傾向をつかむ。
勉強スケジュールを作る上で一番大事な作業です。
合格率10%の行政書士試験に合格するには、
出題傾向を知らなければ勝機はありません。
行政書士試験は、
憲法・民法・行政法・商法・会社法、
行政書士業務に関わる一般知識と、
色々な法律が出題される試験です。
しかし、出題傾向を分析すると、
民法・行政法に偏った試験なのです。
民法・行政法だけで188点あるので、
極端な話この2科目で満点を取れば、
合格点を超える試験になっているのです。
まんべんなく全科目を勉強する必要はありません。
民法・行政法を得点源にする必要があるのです。
4.時期に応じてどんな勉強をするか考える。
行政書士試験に合格するために、
どの時期に何をやるかは決まっています。
8月までには法令の勉強を終えましょう。
9月からは模試を受けるようになり、
10月は総復習の時間を取りましょう。
8月末までは色々な教材で勉強して、
9月以降は新しい教材には手を出さない。
9月以降は復習と模試を受けるイメージです。
私の経験から付け加えると、
知識を入れるインプット学習が終わったら、
問題演習でアウトプットする必要があります。
問題演習の期間は最低でも3ヶ月必要です。
8月までに問題演習まで終わらせ、
9月以降は復習と模試を受けて苦手潰しです。
勉強を始める時期が早ければ、
予定を前倒しすることも可能です。
勉強は始めるのが早いほど有利になります。
5.教材を絞り学習効果の高い勉強スケジュールを組む。
市販の参考書には色々な種類があります。
・入門書
・基本テキスト
・判例集
・六法
・五肢択一式過去問題集
・一問一答(肢別)問題集
・記述式問題集
・直前期総まとめテキスト
・直前予想模試
・年度別過去問題集
・予備校の公開模試
上記すべてに目を通す時間はありません。
教材を絞って勉強すべきです。
使う教材は6つで十分です。
・基本テキスト
・六法
・五肢択一式過去問題集
・記述式問題集
・直前予想模試
・予備校の公開模試
6つの教材を使って、
学力を効果的に上げるスケジュールを作りましょう。
6.勉強の記録を付け教材を適切な時期に使う。
勉強スケジュールまで立てたら実践です。
スケジュールに従って勉強を進め、
毎日の学習内容を記録してください。
「なぜ学習記録をつけるのか」
最初に立てた勉強スケジュール通りに、
勉強できているか確かめるためです。
遅れが出ていたらスケジュールを、
修正する必要があるからです。
スケジュール確認のほかにも、
勉強記録は不安を打ち消す効果があるのです。
勉強をしていると挫けそうになります。
本試験が近づくにつれ不安も大きくなります。
そんなときのお守り代わりにするんです。
「これだけ勉強したんだから大丈夫」
これまでの勉強の足跡が、
あなたに自信をつけてくれます。
正しく教材が使えれば合格点に届きます。
合格するための教材の使い方は7ステップあります。
1.基本テキストを読み込む。
2.五肢択一式過去問題集を解く。
3.別試験の過去問題集を解いて知識を柔軟にする。
4.記述式問題集を解いて知識を深める。
5.直前予想模試を解いて応用力をつける。
6.予備校の公開模試を受けて本番を想定する。
7.勉強したことを総復習する。
順を追って教材を使いこなせるようにしましょう。
一番初めの参考書は基本テキスト
行政書士試験の基本はテキストです。
間違っても問題集からは取り組まないでください。
挫折します。
基本テキスト選びは重要です。
今はどの参考書も行政書士試験で、
合格ラインの180点を取れる情報量が載っています。
どれを選んでも基本的に間違いはありません。
ただし、電子書籍は間違っても選ばないでください。
知識を覚えにくくなり不合格につながります。
基本テキストに似た教材で入門書がありますが、
入門書は選択肢に入れないでください。
必要な知識は基本テキストに載っています。
≫試験まで10ヶ月以上ある場合は入門書からの勉強をおすすめします。
市販の基本テキスト選びは非常に大事
自分が読みやすい参考書であることが何よりも大事です。
・文章の言い回し
・図表の多さ
・レイアウト
どれも読みやすさに影響します。
行政書士試験に合格するなら、
科目が1冊にまとまっている参考書がおすすめです。
授業がない独学では自分で参考書を読むしかないので、
何冊にも分かれていると読み切れないことがあります。
通学・通信講座なら授業がついているので、
テキストを読み切れるように設計されています。
まずは基本テキストを読み切るところから始めましょう。
文章を読み飛ばさない工夫をする|声に出して読み上げるのが効果的
「文字を読むのが苦手で文章を読み飛ばしてしまう」
私も勉強嫌いだったので、
テキストの文字を読み飛ばしてしまいました。
読み飛ばさないように工夫しましょう。
文章に定規を当てる。
指で文字をなぞる。
声に出して読み上げる。
文字をきちんと追えるようにしましょう。
声に出すなら録音すると効果的です。
基本テキストを開かなくても勉強ができるようになります。
最初は行政書士試験で何が問われるのか。
頻出分野はどれかわからない状態です。
基本テキストは重要分野も教えてくれます。
問題集に取り組む前に2回は読んで、
なんとなく行政書士試験の全体像をつかみましょう。
テキストを読みながらノートを作るのは挫折の原因
テキストを読むときに、
ノートは絶対に作らないでください。
すぐに勉強が嫌になり挫折します。
「え?勉強するならノートいるでしょ」
ノートが必要なのは、
先生が黒板で授業を行う学校だけです。
必要な知識はテキストに書いてあるので、
新しくノートに書く必要はありません。
≫勉強に挫折する一番の理由がノート作りなんです。
どうしても書き込みたい知識が出てきたら、
テキストに書き込んでください。
ノートを作るのは時間の無駄と心得ましょう。
テキストをはじめに読むのは、
試験の全体像を知るためです。
大枠を知ってから細かい知識を埋めていく。
これが効率の良い勉強法です。
テキストを読むときはなんとなくの理解で構いません。
単元ごとに6割ぐらい理解しただろう、
という適当さでどんどん読み進めましょう。
五肢択一式過去問題集を解いて知識を定着させる
基本テキストを読み終わったら、
五肢択一式過去問題集に取り組みましょう。
テキストと同じシリーズの問題集を使いましょう。
テキストと問題集の内容がリンクしているので、
学習効率を上げることができます。
五肢択一式過去問題集に取り組むときは、
基本テキストを読み、すぐに問題集を解いてください。
「え?そんなことして意味あるの?」
意外かもしれませんがテキストを読んだ直後に、
すぐ問題を解くことが一番効率がいいんです。
問題集を解く目的は、
知識の定着度を確認するためです。
テキストを読んだだけでは細かい部分は覚えていません。
勉強の早い段階で、
テキストの知識がどのように出題されるのか、
知って勉強を進めることが一番効率的なのです。
学校の勉強を思い出してください。
特に数学は新しいことを学ぶたびに、
問題を解いていたと思います。
習ったことを覚えているか確認し、
間違えたところを復習していたのです。
知識を入れ問題を解くことを、
短期間で行うことで知識の定着を、
早くすることができるんです。
問題集と基本テキストを交互に使って知識を深める
問題集1回目はテキストを読んですぐに問題を解きましょう。
2回目はテキストを見ずに問題を解いて、
分からないところはテキストで復習です。
テキストと問題集を交互に勉強することで、
他の受験生に圧倒的な差をつけて、
知識を身に着けることができます。
問題集を2回解いて、
全体の8割ほど正解していれば。
勉強法は間違っていません。
3回目は総復習のために、
いったん参考書シリーズの問題集から離れましょう。
≫五肢択一式だからこそ暗記に頼っていないか確認しながら勉強しましょう。
別試験の問題集を解いて知識を増やす|別角度からの出題にも対応できるようにする
行政書士参考書シリーズの五肢択一式過去問題集では、
圧倒的に問題量が少ない科目があります。
「行政法」と「民法」です。
過去10年分の問題を解いても、
行政法は190問、民法は90問です。
大量の問題を解いているように感じますが、
「行政法」も「民法」も分野が広いため、
合格するために必要な演習量が足りません。
「行政法」と「民法」は行政書士試験でも、
6割以上の出題がある科目です。
民法と行政法の知識を強化するために、
もう一つ別の問題集を使いましょう。
公務員試験用の五肢択一式過去問題集です。
行政書士試験と公務員試験の問題レベルは似通っています。
これは、私が公務員の受験指導をしていたので事実です。
別試験の問題集を使って言い回しを変えられても答えられるようにする
別試験の問題を解くことは、知識を増やすほかに、
知識を柔軟に使えるようにする目的があります。
勉強を進めていくと、
「知っているのに解けない」
ということが起こります。
算数で例えるなら、
「5×4=□」の問題は答えられるのに、
「5×□=20」の問題は答えられない、
という現象が起こるのです。
「今までと違う!」
と、脳が混乱して正しい答えを導けなくなるのです。
知っていたのに解けなかったでは泣くに泣けません。
同じ参考書を使っていると、
言い回しに慣れてきます。
別の言い回しでも得点できるように、
公務員試験の問題集で知識を柔軟にしましょう。
記述式問題集を使って知識をより深化させる
記述式の得点は全部で60点です。
試験全体の2割の得点を占めるので、
記述の対策をしておきましょう。
五肢択一式問題の理解も深まるため、
1冊で良いので記述式問題集に取り組んでください。
記述式は1から自分で解答を作ります。
五肢択一式問題のように、
1つ正解がある問題ではありません。
自分で答えられる完璧な知識が必要です。
記述式問題集に取り組むことで、
「五肢択一式のこの問題、記述ならこれがキーワードになるだろうな」
と、想像力を深めて勉強できるようになります。
記述式問題集も2週は必ず取り組みましょう。
直前予想模試を解いて蓄えた知識を自在に使えるようにする
本試験では過去問題は出題されません。
五肢択一式問題集があらかた終わったら、
すぐに直前予想模試に取り掛かりましょう。
直前予想模試で間違えたところを復習しながら、
五肢択一式問題集を完璧に仕上げて取り組むイメージです。
直前予想模試の良いところは、
過去問ではないというところです。
疑似的に本試験を体験することができます。
今まで積み上げてきた知識が通用するか直前予想模試で確認しましょう。
直前予想模試に最低1冊は取り組もう
「ちなみに、どのくらいの量を解けばいいの?」
どんなにペースが速くても2週間に1回が限度です。
それ以上のペースでは取り組む意味がありません。
直前予想模試は知識を取り入れるというよりは、
今までの勉強で定着していない知識がないか確認する、
という目的が大きいことを忘れないでください。
今までの勉強法と目的が違うんです。
直前予想模試は、
どの出版社が販売しているものでも構いません。
最低でも1冊は解いておきたいです。
本番を意識するために予備校の公開模試を受ける
本番を想定するために公開模試を受けましょう。
時間も本試験と同じ時間に設定されていますから、
会場で受験すべきです。
色々な人がいる中で、
決められた時間で問題を解くことに慣れ、
本試験ではどのように行動するのかシミュレーションするのです。
最低でも3社の公開模試を受けたいです。
行政書士試験で、
どの分野が狙われるのか比べるためです。
予備校同士で同じ分野から出題があれば、
行政書士試験で何が狙われるのか判断ができます。
公開模試を受けることで、
自分が受験生の中で、どの位置にいるのか、
合格できる学力が付いているかが、わかるようになります。
これが勉強へのモチベーションにつながるんです。
模試を受験する人たちは、
本気で行政書士試験に合格したい。
と思っている人たちばかりです。
あなたの成績が、
公開模試で上位30%に入っていれば、
今までの勉強法は間違いではないと思って大丈夫です。
自分の立ち位置を知るためにも、
早めに公開模試を受けることが重要なのです。
最後の最後は総復習をして勉強納めを視野に入れる
今までいろいろな教材に取り組んできました。
知識を100%の理解度にする必要があります。
秋に差し掛かったら総復習をしましょう。
1ヶ月以上開いていないテキストや問題集があるはずです。
今まで手を付けた教材を一気に復習して、
合格できるだけの知識に昇華するのです。
地道な作業ですが手を抜くことはできません。
総復習という勉強法を実践することで、
初めて点数が跳ね上がります。
この時期では「何をやらないか」を決めてください。
総復習の期間はおおよそ1ヶ月。
今までの参考書を振り返るにしても量が多い。
本当に重要度の高いものだけ実践してください。
絶対にやるべき事を書き出して、
一つ一つこなしていくのです。
≫直前期に総復習をすることで得点力を大幅に上げることができます。
7.本試験前日・当日の動きを確認する。
意外に軽視しがちなのが本試験前日・当日の過ごし方です。
ここまでしっかり積み上げてきたものが、
本番で崩れてしまっては意味がありません。
前日・当日の準備はしっかり行いましょう。
行政書士試験は前日から始まっています。
≫最高のコンディションで受験するためにも前日の準備は怠らないように。
試験日前日に持ち物を準備しておけば、
忘れ物をしたり不測の事態が起きても、
ます慌てることはありません。
試験当日は入室・退室禁止時間が決められていたり、
試験中の飲食は禁止されていたりします。
「そんなこと知らなかった」
とならないためにも、
≫当日のスケジュールを入念に確認しておきましょう。
本試験でどうしても解答ができない問題は裏ワザを使う
本試験では見たことのない問題が出題されます。
どんなに勉強したといっても、
行政書士試験は合格率10%の試験です。
答えがわからない問題にも出会うはずです。
本当にどうしても解答できない問題には、
五肢択一式を逆手に取った裏ワザを使いましょう。
問題の中に一つ答えがあるのが五肢択一式問題です。
こういった問題を作るときは最初に正解肢を作って、
あとから間違いの問題を作るんです。
正しい問題文を作った後に、
一部だけ変えてしまえば間違い肢の完成です。
■数字の入れ替え
■用語の入れ替え
■極端な断定、または、否定
上記3つを手掛かりに問題を解くことができるんです。
本試験が終わったら当日痛に自己採点をする
行政書士試験当日は、
各予備校の解答速報がインターネットに掲載されます。
必ず自己採点をして今後の方針を決めましょう。
合格発表を待っていては時間がもったいないです。
行政書士試験に合格するためには練りに練った勉強法が必須

働きながら行政書士試験に合格するには戦略が必要です。
それも練りに練った勉強法を実践しなければ、
合格はありえません。
7つの合格に必要な要素を分解して話しました。
1.なぜ行政書士試験を受けるのか目的を明確にする。
2.試験制度を確認し本試験までの工程を理解する。
3.試験の出題範囲を分析して傾向をつかむ。
4.時期に応じてどんな勉強をするか考える。
5.教材を絞り学習効果の高い勉強スケジュールを組む。
6.勉強の記録を付け教材を適切な時期に使う。
7.本試験前日・当日の動きを確認する。
行政書士試験は自問自答の繰り返しです。
「この勉強法であっているのか」
「今やるべきことな何なのか」
不安を消してくれるのが練りに練った戦略。
勝率を上げる勉強法なのです。
しかし、自分で勉強するのが不安だという人は、
予備校を活用して合格を目指しましょう。
合格戦略を練ることは誰にでもできます。
しかし、ほとんどの人は戦略を立てません。
すぐに目の前の問題集を解き始めます。
正直なところ戦略を考えるのは面倒だ、
と思う人が大半でしょう。
しかし、合格率10%の試験です。
他人と同じことをしても合格できません。
合格するために必要なことを積み上げましょう。
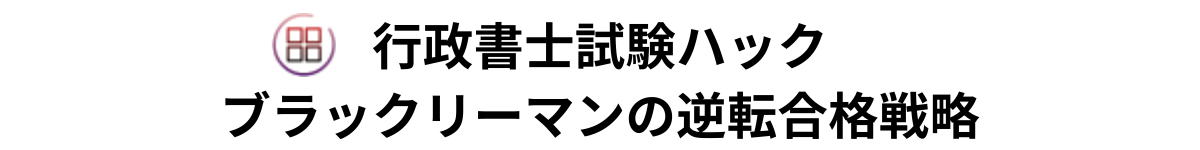
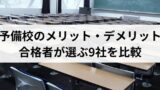
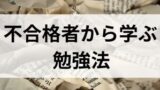
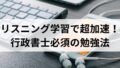

コメント