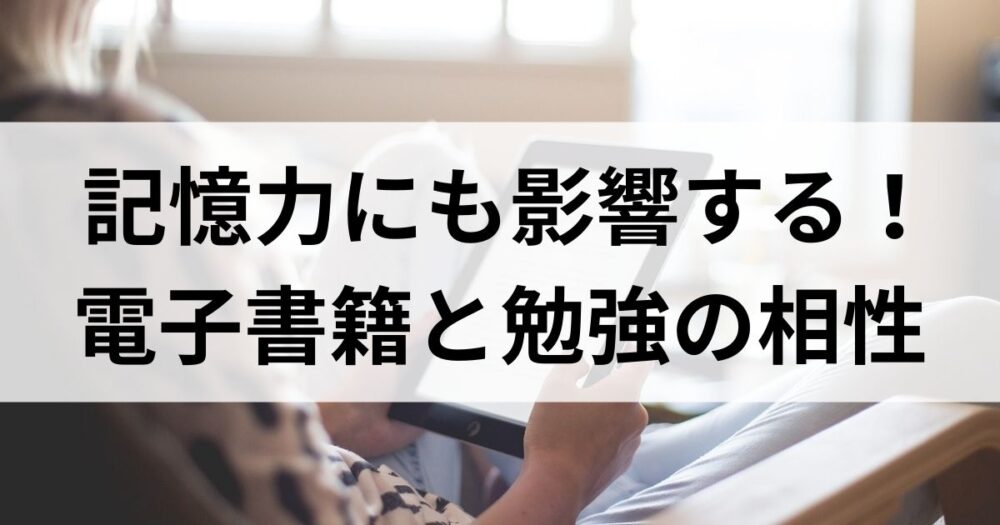
行政書士の参考書もKindle版の販売が増えています。
電子書籍の方が神の参考書よりも
持ち運びしやすく、価格も安いため、
電子書籍の方が良さそうに思います。
私も小説はKindle派になりました。
しかし、電子書籍は行政書士の勉強に悪影響がある。
と、私が言ったらどうでしょうか。
「いやいや、いまどきスマホを使うんだから電子書籍で十分でしょ」
と思っていると勉強効率が悪くなるかもしれません。
電子書籍は行政書士試験に必要な3つの勉強ができない
電子書籍も使い勝手が良くなっていますが、
それでも行政書士試験の勉強をするならば、
紙の参考書をおすすめします。
なぜ、私が紙の参考書にこだわるのか。
勉強に必要なことが電子書籍ではできないからです。
■パラパラとページをめくることができない
■五感の刺激が弱いため記憶に残りにくい
■すぐに書き込みができない
この3つが電子書籍ではできないので勉強の効率が下がるのです。
電子書籍と記憶に関する興味深い研究
さらに、興味深い研究結果があります。
ノルウェーのスタヴァンゲル大学では、2組の生徒に、
1組には電子書籍、もう1組には紙の本で物語を読ませたとき、
紙の本を使って読書をしたグループの方が本の内容の理解力が高い。
つまり、紙の本の方が記憶に残りやすいと結論付けています。
参考リンク:https://www.theguardian.com/books/2014/aug/19/readers-absorb-less-kindles-paper-study-plot-ereader-digitisation(2024.2.2確認)
また、情報処理学会では、
電子書籍と紙の本の効果について論文を出しています。
電子書籍は文字の鮮明さやページのめくりやすさがメリットであるが、
紙の本では、読書時に集中しやすく理解度も高かったとされています。
参考リンク:https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=81257&item_no=1&page_id=13&block_id=8(2024.2.2確認)
電子書籍は手軽で使い勝手の良いものですが、
勉強する上で大切な理解力で比べると、
影響が出ていることが分かります。
行政書士試験では紙の参考書の方が勉強効率がいいんです。
効率の良い勉強をするなら紙の参考書が有効
電子書籍は中身を知られずに読めるという利点があります。
私も行政書士受験性の時、外で勉強するときは、
参考書にカバーをかけてわからないようにしていました。
しかし、働きながら限られた時間で合格するには、
無駄をそぎ落とした効率が良い勉強が必要です。
電子書籍は効率の良い勉強教材とは言えません。
なぜ、電子書籍では紙の本より理解力が落ちるのか。
それは3つのポイントがあります。
■ パラパラ読みで重要ポイントを抑える
■ 触覚を使って記憶を強化する
■ 手軽に書き込んで参考書の学習効果を上げる
この3つが効率的な勉強に欠かせないのですが、
電子書籍ではできないので効率が悪くなるんです。
パラパラ読みで重要ポイントを抑える
紙の参考書と電子書籍の大きな違いはページのめくり方です。
「この内容って前のページに書いてあったよな」
と思ったとき、紙の参考書ならば、
パラパラとページをめくって探すことができます。
この作業が行政書士試験の勉強で非常に重要なのです。
行政書士試験本番で、
「参考書のあのあたりに書いてあったことだ」
と、勉強した行政書士試験の知識が、
イメージとして残りやすくなるんです。
電子書籍が勉強の効率を下げるのが問題集です。
問題と解答が分かれている参考書だと最悪です。
すぐに答えを見れないので、わずらわしく感じます。
マニュアル程度なら電子書籍でもいいのですが、
ページを行き来する可能性が高い専門書は、
電子書籍の購入はおすすめしません。
行政書士試験の参考書は紙の本を選びましょう。
触覚を使って記憶を強化する
電子書籍もページをめくる動作はしますが、
紙の参考書だと感覚を使います。
ページをめくるときの感触や、
今、自分が参考書のどこを勉強しているのか、
本の厚みも記憶するため、内容が頭に残りやすくなります。
「前にも同じ内容が書いてあったな」
と、参考書のどこに書いてあったのかを、
感覚的に覚えているため、すぐに探すことができ、
知識の確認作業を終わらすことができます。
行政書士の問題集を解いている時も同じです。
問題集で間違えたときは
テキストで覚え直しをする必要があります。
その時も「大体ここら辺に書いてあった」と、
あたりをつけて探すことができます。
電子書籍だとこの確認作業で、もたつくんです。
行政書士試験のテキストは500ページを超えます。
調べ直すとなると電子書籍はかなり不向きなのです。
手軽に書き込んで参考書の学習効果を上げる
「電子書籍でも書き込みぐらいできるだろう」
電子書籍もマーカーを引いたり、メモ機能がついています。
ただ、参考書に書き込みすることが目的ではないはずです。
知らない知識を書き足して、後ですぐ読み返せるようにする。
行政書士の知識確認をするために、
参考書に書き込みをするのです。
行政書士試験の勉強も総復習の時期になると、
マーカーを引いてあるところをチラ見するだけで、
何を勉強したのか思い出せるレベルにまで反射的に反応できなければいけません。
書き込んだ知識も確認したいのに、
メモ機能だと書き込んだ内容をすぐに確認できないんです。
行政書士のテキストに書いていない知識が出てきたとき、
持っているシャーペンで直接書き込みたくなります。
電子書籍だとできないので、私はまどろっこしいと感じてしまいます。
行政書士の勉強をしているときは、
できるだけ作業の時間を減らしたいんです。
そうなると、アナログの方が効率が良くなります。
行政書士の勉強法では紙の参考書がおすすめ
電子書籍で実際に勉強を進めていくと、
ちょっとした手間が煩わしくなってきます。
時間がない中、
効率よく参考書の内容を頭に詰め込むには、
目だけでなく色々な感覚を駆使して覚えていく方が効率がいいのです。
■パラパラとページをめくることができる
■五感の刺激があるため記憶に残りやすい
■すぐに書き込みができる
電子書籍は、何冊も本を持ち歩けることがメリットです。
ただ、行政書士試験の勉強をするときには、
電子書籍のデメリットの方が勝ります。
限られた時間で効率よく勉強するならば、
紙の参考書を使った勉強をおすすめします。
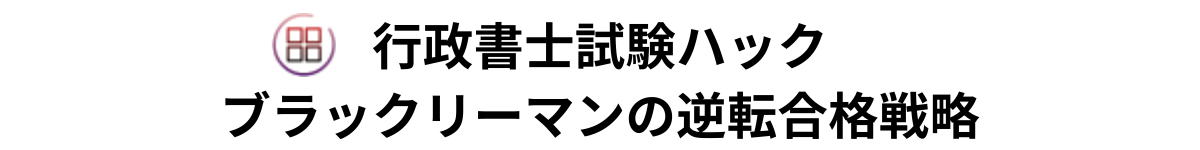
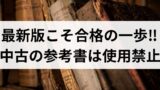
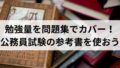
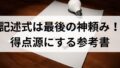
コメント