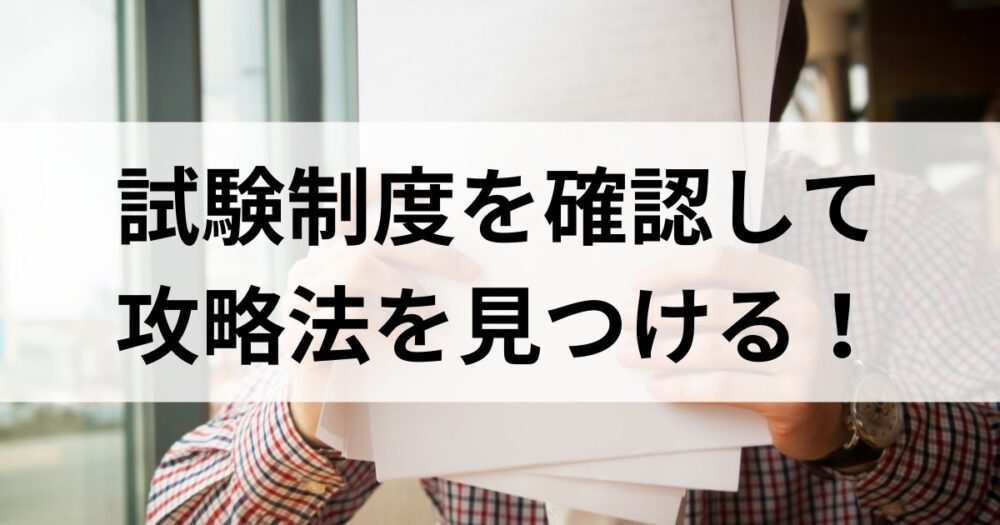
行政書士試験を受けると決めたら何をしますか。
「まずは参考書を読んでいこう」
と、始めると途中で挫折します。
私は試験日程を確認しないまま勉強を始めました。
本試験日を知らずに行政書士試験は受けられません。
試験内容も知らずに合格はできないのです。
10人に1人は不合格になる試験です。
何年も必死で勉強しても不合格、
公開模試で200点を超えていても、
いざ本番になると実力を発揮できず、
不合格になる人もいるくらいです。
行政書士試験にすべてを注ぎ込んでも、
学習量の多さに挫折することすらあります。
1年で合格できる試験ですが、
効率よく勉強しなければ学力が付きません。
行政書士試験の内容を知らなければ、
無駄な勉強をして不合格になるんです。
試験内容を分析し、
戦略的に勉強を進めることが、
行政書士試験合格の第一歩です。
行政書士試験の内容を知らずして合格はない

行政書士になるためには試験内容を知る必要があります。
どんな科目が、どんな形式で出題されるのか。
配点の偏りはあるのか。注力すべき科目はどれか。
合格点を取るために、いかに効率の良い勉強ができるか。
戦略を練った効率的な勉強法が必要です。
問題の出題内容だけでなく、
本試験日や、申込み締切日など、
試験の日程も知っておくべきです。
年1回の行政書士試験です。
受験申込み忘れがあっては目も当てられません。
合格した後、資格が活かせるのか。
活かすためにはどうすれば良いのか。
知っておかないと勉強のやる気に影響します。
行政書士試験に合格したあとに、
本当に自分の目標を達成できる資格なのか。
試験勉強を始める前に仕事内容をイメージできると、
途中で挫折する可能性を下げることができます。
≫行政書士の専門分野は3つ。仕事内容をイメージできると挫折する可能性を下げられます。
行政書士とは?行政書士法に基づく国家資格者

行政書士試験に合格するために、
職業の内容を知っておきましょう。
行政書士は議員立法と呼ばれる、行政書士法に基づいた職業です。
国民が必要としているから作られた資格なんです。
行政書士の業務内容は、
他人の依頼を受け報酬を得て、
■ 役所に提出する許認可等申請書類、手続代理
■ 遺言書などの権利義務に関わる書類
■ 事実証明・契約書の書類作成
を行う職業です。
行政書士は複雑化する社会に合わせて、
書類代筆だけでなくコンサルティングを含んだ、
許認可手続き業務の専門家として期待されています。
行政書士試験の日程・範囲・受験資格は必ず確認
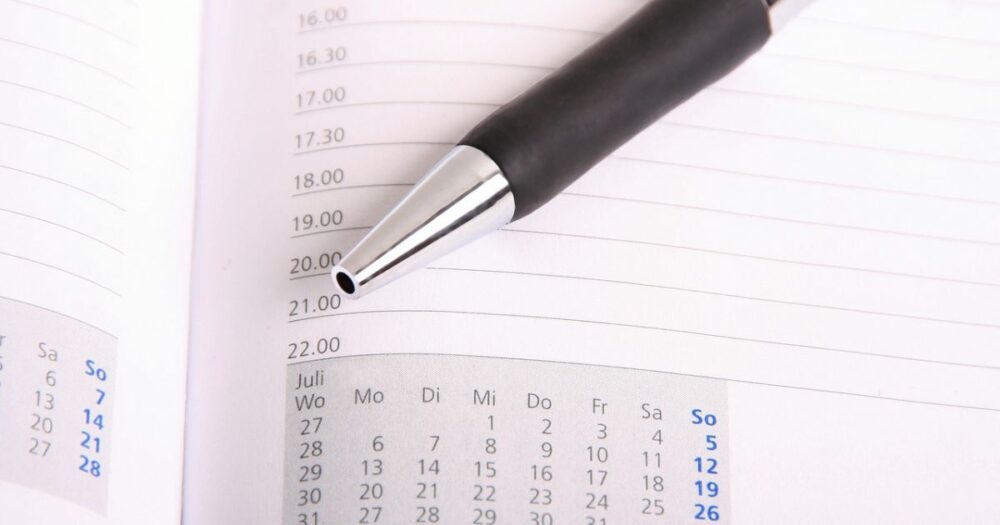
行政書士試験の勉強を始める前に知っておくべき内容は4つです。
■ 本試験日までの日程
■ 出題科目と範囲
■ 受験資格の有無
■ 合格基準と合格率
行政書士試験合格までの日程|申込みを忘れないようにチェック
行政書士試験の日程内容は次の通りです。
| 試験の公示 | 7月上旬(例年) |
| 願書配布・申込期間 | 7月下旬~8月下旬(例年) ※郵送(消印有効)とインターネット申込両方が可能。 インターネット申込は郵送申込より数日早めに締切られます。 インターネット申込の場合締切当日17時までの申請が有効。 |
| 受験票到着 | 10月下旬(例年) |
| 本試験日 | 11月第2日曜日(例年) |
| 試験時間 | 13時~16時までの3時間(例年) ※入室受付は12時30分まで。以降試験の説明が始まります。 |
| 合格発表 | 1月末(例年) |
| 合格証到着 | 2月下旬までに完了(例年) |
| 受験手数料 | 1万400円 |
| 受験資格 | 年齢、学歴、国籍等に関係なく誰でも受験可 |
毎年、具体的な試験日時は、
一般財団法人行政書士試験研究センターに、
掲載されるので7月になったら確認しましょう。
≫各日程で具体的にどんな動きをするのか事前にシミュレーションすることも大切です。
科目の出題形式と出題範囲を分析してわかる合格の秘訣
行政書士試験に最短合格するためには、
どんな科目があり、どのように出題されるのか、
知っておかなければ不合格になります。
科目ごとの配点や特徴を知ることで、合格の突破口が見えてきます。
出題形式は3つ|五肢択一式、多肢選択式、記述式
行政書士試験の出題形式は3つあります。
| 出題形式 | 内容 | 配点 | 総合点 |
| 五肢択一式 (ごしたくいつしき) | 5つの選択肢から1つの正解を選ぶ | 1問/4点 | 54問/ 216点 |
| 多肢選択式 (たしせんたくしき) | 決められた語句20個の選択肢から文章中 の空欄ア~エに当てはまる語句を選ぶ | 1問/8点 (1選択肢2点) | 3問/ 24点 |
| 記述式 (きじゅつしき) | 設問に対して40文字程度で解答を作る | 1問/20点 (部分点あり) | 3問/ 60点 |
行政書士試験に合格するためには、
五肢択一式問題の攻略が必須です。
記述式の大きな配点に目が行きがちですが、
行政書士試験の大部分を占める五肢択一式で、
しっかり点を取れるように学習していきましょう。
出題範囲と出題内容を分析すると民法と行政法が得点源
▼行政書士試験の出題範囲と内容を分析した表▼
| 出題科目 | 出題内容と対策 | 出題数 | 配点 | 合計点 | |||
| 五肢択一式 | 多肢選択式 | 記述式 | |||||
| 行政書士の 業務に関し 必要な法令 | 基礎法学 | 法律の基礎知識について幅広く出 題される。(法制史、司法制度改革 、法律用語など) | 2問 | ― | ― | 8点 | 46問/ 244点 |
| 憲法 | 人権と統治からの出題がほとんど で、条文と判例の知識が中心に出 題される。 | 5問 | 1問 | ― | 28点 | ||
| 民法 | 1000条の条文のうち200条が出題 される。事例問題が多く出題さ れる。 | 9問 | ― | 2問 | 76点 | ||
| 行政法 | 行政法の一般的な法理論行政手続 法、行政不服審査法、行政事件訴 訟法、国家賠償法、地方自治法が 出題される。条文と判例の知識を 詳細に問われる。 | 19問 | 2問 | 1問 | 112点 | ||
| 商法・会社法 | 条文知識を問う出題が多い。 | 5問 | ― | ― | 20点 | ||
| 行政書士の 業務に関し 必要な基礎 知識 | 行政書士関連法 | 行政書士法等行政書士業務と密接 に関連する諸法令が出題される。 | 3問 | ― | ― | 12点 | 14問/ 56点 |
| 一般知識 | 全国共通テストレベルの政治・ 経済・社会の問題が幅広く出題 される | 4問 | ― | ― | 16点 | ||
| 情報通信・ 個人情報保護法 | IT用語や情報通信に関わる用語、 個人情報保護法から出題される。 | 4問 | ― | ― | 16点 | ||
| 文章理解 | 現代文の長文読解問題。文章の並 び替え・空欄補充・稀に要旨理解 問題が出題される。 | 3問 | ― | ― | 12点 | ||
| 合計 | 54問 | 3問 | 3問 | 300点 | 60問 | ||
| 216点 | 24点 | 60点 | |||||
行政書士試験は民法と行政法に配点が偏っています。
内容を見てみると、
行政法で112点、民法で76点。
合計188点で行政書士試験合格です。
全体の6割を占める行政法・民法を、
得点源にすることが合格に必要です。
出題内容をしっかり分析すると、
行政書士試験の配点の偏りがわかり、
メリハリある勉強で合格を狙えるのです。
≫傾向・配点を踏まえて科目ごとに戦略を練った勉強法を実践しなければ合格はあり得ません。
受験資格と欠格事由は行政書士試験受験生には関係ない
行政書士試験を受験する場合、
受験資格の欠格事由はありません。
誰でも受験することができます。
もう一つ受験するときに気になるのが、
免除科目があるのかどうか。
国家資格によっては、
ある資格を持っていると、
受験を免除される科目があります。
行政書士試験では免除科目はありません。
誰でも受験できる試験なので、
免除科目を作りようがありません。
ただ、行政書士の資格を持っていると、
資格によっては免除される科目があるので、
行政書士試験に合格した後に別の資格も取る、
という人は確認しておきましょう。
合格基準と合格率を確認して試験の難易度を知る
行政書士試験は180点で合格です。
ただ、3つの合格基準を満たす必要があります。
■ 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50%(122点)以上である者
■ 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40%(24点)以上である者
■ 試験全体の得点が、満点の60%(180点)以上である者
細かい内容になっていますが、
■ 合格ラインは180点
■ 基礎知識で24点取る必要がある。
この2点を抑えておけば十分です。
行政書士試験の合格率は10%で推移している
最近10年間の合格率推移を表にまとめました。
| 年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2023年度 | 59,460人 | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |
| 2022年度 | 60,479人 | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |
| 2021年度 | 61,869人 | 47,870人 | 5,353人 | 11.18% |
| 2020年度 | 54,847人 | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |
| 2019年度 | 52,386人 | 39,821人 | 4,571人 | 11.48% |
| 2018年度 | 50,926人 | 39,105人 | 4,968人 | 12.70% |
| 2017年度 | 52,214人 | 40,449人 | 6,360人 | 15.72% |
| 2016年度 | 53,456人 | 41,053人 | 4,084人 | 9.95% |
| 2015年度 | 56,965人 | 44,366人 | 5,820人 | 13.12% |
| 2014年度 | 62,172人 | 48,869人 | 4,043人 | 8.27% |
| 2013年度 | 70,896人 | 55,436人 | 5,597人 | 10.10% |
毎年、4万人が試験を受け、
4千人が合格する内容になっています。
1万人は受験を諦めていることもわかります。
受験の壁が高い行政書士試験ですが、
毎年10%の合格率に収まっているのが特徴的です。
≫行政書士試験の合格率が10%になる理由には受験生の行動も関係しています。
合格のために取るべき勉強法は通学・通信・独学の3つ

行政書士の試験内容を知った後は、
どの勉強法で合格を勝ち取るか考えましょう。
行政書士試験に合格するために3つの勉強法があります。
■ 予備校に通学する
■ 通信講座を受ける
■ 独学で勉強する
これらの特徴を踏まえて、最短で合格できる勉強法を探しましょう。
≫通学・通信・独学の3つ勉強法のメリット・デメリットをよく考える必要があります。
予備校に通学する|学習サポートが充実している
一番オーソドックスな勉強法は、
予備校に通って勉強することです。
勉強教材は揃えられていますし、
丁寧に教えてくれる講師もいます。
わからないところは講師に直接聞けますし、
教室に行けば行政書士を目指す受験生がいます。
切磋琢磨して勉強ができる環境が手に入れることができます。
1年と言う短い時間ですが、
勉強で挫折するのに十分な時間です。
誰かと一緒に勉強することが、
勉強へのモチベーションにもつながり、
合格へ1歩も2歩も近づけてくれます。
大手予備校では教室に通える、
通学講座を開講しているところが多いので、
強制的に勉強の習慣を身に着けることができます。
勉強に不安がある人は大手予備校のサポートを受けましょう。
通信講座を受ける|サポート内容に注意して選ぼう
「予備校には通えないけど、予備校の教材で勉強したい」
と、思っているならば通信講座をおすすめします。
最近は通信講座に特化した予備校が増えています。
サポート内容も大手予備校顔負けの手厚さなので、
自分が求めている勉強環境を見つけることもできます。
教材がすべて自宅に届くので、
場所にとらわれず勉強することが可能です。
一方で、
教室に通って勉強する機会がないので、
自分で勉強ペースを管理する必要があります。
自己管理が苦手な人にとって、一番の挫折理由になる要素です。
注意すべきことは金額とサポートの内容です。
通信講座は値段が5~30万円とピンキリです。
中には、教材だけで授業はない、ということもあります。
通信講座に申し込むときは、
あなたが持っているイメージとのズレをなくすために、
サポート内容にもしっかり目を光らせる必要があります。
独学で勉強する|一番手っ取り早く勉強ができるが一番挫折しやすい
独学は一番お金がかからない勉強法です。
ただし、通学や通信講座と違い、
使う教材は自分で用意する必要がありますし、
行政書士試験の最新情報を手に入れるのが大変です。
全てがカスタマイズできる自由さがある反面、
一番挫折しやすい勉強法です。
正しい勉強法を知り、
効率的に勉強ができるのであれば、
一番かかる費用が安く済むだけでなく、
あなたに合った勉強法を確立することができます。
人生をかけて行政書士になりたい、
だけど予備校の通学・通信講座に申し込むお金がない。
そんな熱量にあふれたあなたには、
お金がないという理由で諦めてほしくありません。
独学で合格するために最善の勉強法を考えましょう。
行政書士試験は試験内容を知って最短合格を目指す

行政書士試験の内容を知ることが合格の早道です。
1回目の受験で合格するには欠かせません。
人生を変えるかもしれない行政書士試験。
真っ先に参考書を選ぶのではなく、
行政書士試験とは何か、どんな試験なのか。
内容を確認して合格するための戦略を考えましょう。
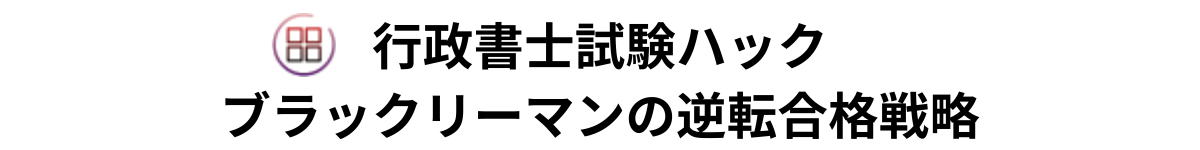
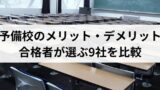
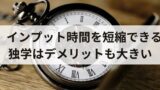
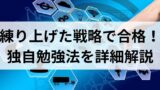
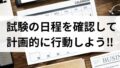
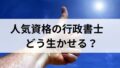
コメント