行政書士試験は、多くの人が挑戦する人気の国家資格試験です。しかし、難易度や合格率、必要な勉強時間などについて不安を抱える受験生は多いです。本記事では、行政書士試験の難易度や合格率、他の資格との比較、必要な勉強時間について詳しく解説します。
記事を読めば、行政書士試験の全体像を把握し、効果的な学習計画を立てることが可能です。行政書士試験の合格率は約10%前後で推移しており、簡単な試験ではありません。しかし、適切な学習方法を知り、十分な勉強時間を確保することで、働きながらでも合格を目指せます。
行政書士試験の難易度と合格率

行政書士試験は、”法律系資格試験の中では”比較的難易度が低く登竜門的な位置づけです。受験資格に学歴や年齢の制限がないため、誰でも受験できる点が魅力です。試験は7科目あり、合格基準は総合得点の60%以上で、試験時間は3時間です。勉強する範囲は多いですが、ポイントを絞って勉強することで働きながらでも1年程度の準備期間があれば合格できます。
行政書士試験の難易度
行政書士試験の合格率は約10%前後で推移しているため、簡単な試験ではありません。なぜ難しいのか。理由は以下の3つです。
- 暗記量が多く思考力を問われる出題が多い
- 択一式問題と記述式問題の両方ある
- 時事問題も出題される
試験に合格するためには、各科目を得点できるバランスの良い学習が求められます。法律の基礎知識がない人は、法律特有の言い回しに慣れることが必須です。対策としては、過去問の分析や対策、苦手科目の重点学習がおすすめです。難しい試験ですが、適切な対策を行えば合格の可能性は十分あります。
行政書士試験の合格率
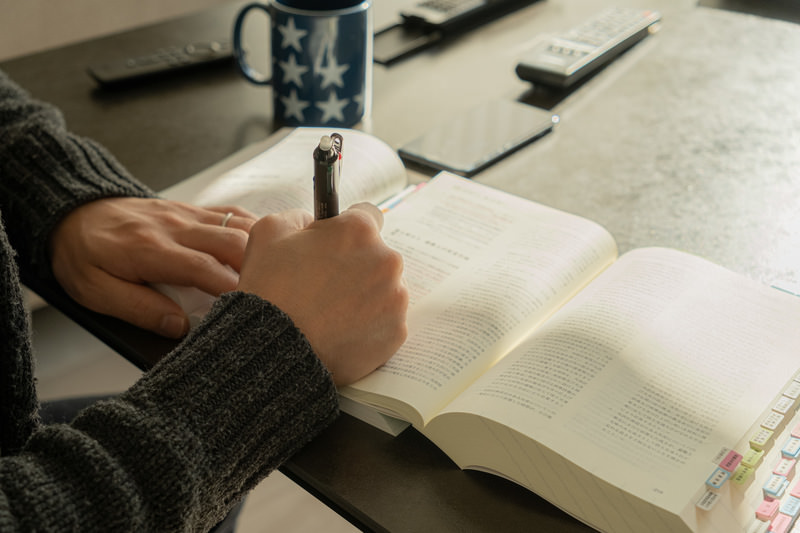
行政書士試験の合格率は、2021年が11.2%、2022年は12.1%、2023年は14.0%と例年10%程度で推移しています。受験者数は年間約4万人で、合格者数は年間約4,000〜5,000人です。近年は若干合格率が上昇傾向にあるものの、難関試験であることに変わりありません。
他の国家資格と比較すると、行政書士試験は中程度の難易度です。合格を目指すには十分な準備と努力が必要です。
合格率の推移
行政書士試験の合格率は、過去10年間で8~15%の間を推移しています。2014年度に8.3%と最低の合格率を記録し、2017年度には15.7%と最高の合格率を記録しました。近年は11%程度で安定傾向にあります。受験者数は年々増加傾向ですが、合格者数はほぼ横ばいで、試験の難易度は一定に保たれています。
直近5年間の平均合格率は約11%です。年度によって多少の変動はありますが、大きな難易度の変化は見られません。コンスタントな勉強を続けることが合格への近道です。
他の資格と比較した行政書士試験の難易度

行政書士試験の難易度は、以下の法律系資格と比べて比較的取得しやすい水準にあります。法律資格の登竜門とまで言われています。働きながらの受験や独学での合格も可能で、働き盛りの30歳の合格率が多い試験です。他の試験と比較した難易度は以下のとおりです。
宅地建物取引士(宅建)試験
宅地建物取引士(宅建)試験は、不動産取引に関する専門知識を問う国家資格試験です。行政書士試験と比べるとやや易しいとされています。試験は年1回、10月第3日曜日に実施され、合格率は約15~20%です。試験は4肢択一式のみで、試験時間は計2時間です。
50問の択一式問題があり、合格基準は50問中37問以上正解する必要があります。総合得点の74%以上が合格ラインです。宅建試験は実務経験不要で受験できるので、働きながら学習できる資格として人気です。合格すると、登録後に宅地建物取引業者として活動できます。試験科目は以下のとおりです。
- 民法等
- 宅建業法
- 法令上の制限
- その他関連知識
宅建資格は不動産取引の仲介や代理に必要で、賃貸・売買契約の重要事項説明を行う際に活用されます。
社会保険労務士(社労士)試験

社会保険労務士(社労士)試験は、労働・社会保険関連法規の専門家を認定する国家資格試験です。行政書士試験と比較すると、やや難易度が高いとされています。社労士試験は、毎年8月下旬に実施され、合格率は5〜7%です。試験科目は選択式(8科目)と択一式(7科目)の2つの出題形式があり、受験資格に学歴や実務経験などの指定される条件を満たす必要があります。ちなみに行政書士試験合格者は受験資格を満たします。
試験は労働・社会保険関連法規・社会保険関連法規や一般常識、労務管理等を含みます。それぞれの科目で2つの出題形式があり、選択式は8問、択一式は70問の計78問が出題されます。合格基準は2つあり、①選択式で25点以上の得点(62.5%)、②択一式で44点以上の得点(62.9%)が必要です。勉強時間は1000時間が目安と言われており、勉強期間の目安は1年~1年半程度です。独学での合格も可能ですが、通信講座や専門学校の利用が一般的です。
社労士試験が難しい要因は以下のとおりです。
- 労働法や社会保険法の広範な知識が必要である
- 法改正に常に注意を払う必要がある
- 実務的な問題も出題されるため理解力が求められる
社労士試験は、広範な知識と高い理解力が求められる難関試験ですが、準備と努力により合格を目指せます。
司法書士試験
司法書士試験は、法務省が所管する国家資格試験です。毎年7月に実施され、合格率は約3~4%と非常に難関です。試験内容は、民法・商法・会社法・不動産登記法・商業登記法などの法律科目が出題されます。択一式と記述式の形式で出題され、午前は2時間・午後は3時間の試験時間があります。また10月には口述試験もあり難易度に拍車をかけています。
択一式試験は35問出題され、合格基準は通常70%以上の得点が必要です。記述式試験は実務に即した問題が2問出題され、法律知識や文章力が求められます。一般的に3000時間の勉強が必要と言われており、勉強期間は1~2年程度です。独学での合格は難しく、勉強に専念しなければ合格は難しいので、専門学校などでの対策がおすすめです。
働きながら受験する人も多く、仕事と両立しながら勉強できます。合格後は司法書士として開業して、不動産登記や会社設立手続きなどを主な業務として行います。法律の専門家として活躍できる魅力的な資格ですが、難易度が高いので十分な準備が必要です。
税理士試験

税理士試験は、行政書士試験と比べてさらに難易度が高いと言われています。合格率は約10%前後と非常に低く、難関資格の一つです。試験は5つの科目から構成され、会計学2科目と税法3科目に分かれています。全科目の合格が必要ですが、科目ごとの合格制度があるため、部分合格を積み重ね数年かけて資格取得を目指すのが一般的です。
各科目は100点満点で採点され、60点以上が合格基準です。試験は年に1回、8月に実施され、合格までの平均期間は3〜5年と言われています。税理士試験が難しいとされる理由として、以下の点が挙げられます。
- 広範囲の専門知識
- 複雑な計算問題
- 最新情報の習得
働きながら受験する人も多いですが、十分な学習時間の確保が大きな課題です。独学での合格は非常に難しく、多くの受験者は専門学校などを利用して学習しています。税理士としての需要は高く、合格後は安定した収入が期待できます。難易度は高いものの、将来性のある資格です。
中小企業診断士試験
中小企業診断士試験は、行政書士試験と比較してより専門的で難易度が高い資格試験です。合格率は試験全体で約4%前後と低く、難関試験の一つとされています。中小企業診断士試験は、1次試験と2次試験があり、経済学や財務・会計、企業経営理論など幅広い知識が必要です。また1次試験は絶対評価(総得点の60%以上の点数)であるのに対し、2次試験は60%の得点に加えて相対評価なので受験者の上位20%に入る必要があります。
登録のためには実務補習または実務従事が必要で、試験科目が多く学習範囲が広いのが特徴です。合格後のキャリアの幅が広く、独立開業や企業内診断士として活躍できます。試験対策は1年以上の準備期間を必要とするのが一般的で、継続的な学習と更新が必要です。働きながらの受験者が多いのも特徴の一つです。
オンラインでの学習教材や講座が充実しているので、効率的に勉強を進められます。他の国家資格と比べて年収が高い傾向にあるのも魅力の一つです。
行政書士試験の概要

行政書士試験は、毎年11月に実施される国家資格試験です。年齢制限のほか国籍の指定もなく学歴不問で受験できます。試験は合計3時間のマークシート方式と記述式で出題されます。全国47都道府県で受験できます。行政書士試験の概要として以下の点を押さえておきましょう。
- 行政書士試験の試験科目
- 行政書士試験の配点と合格基準
- 行政書士試験の日程と申し込み方法
行政書士試験の試験科目
行政書士試験の試験科目は、行政書士として必要な法律知識や一般教養を幅広くカバーしています。試験科目で問われる知識は、以下のとおりです。
- 憲法と行政法
- 行政書士の業務の基礎となる知識
- 民法や商法
- 法律関係の理解
- 基礎法学
- 法律の基本的な考え方
- 一般知識等
- 政治・経済・社会に関する幅広い知識
- 文章理解
- 実務で必要な文書作成能力
- 情報通信・個人情報保護
- 情報や通信技術に関する基本的な用語知識
- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
- 行政書士法や戸籍法などの理解
科目をバランス良く学習することが、試験合格への近道です。各科目の配点を意識しながら、効率的に学習を進めましょう。
» 行政書士試験の科目・試験免除制度について解説!
行政書士試験の配点と合格基準

行政書士試験の総得点は300点満点で、合格するには総得点の60%以上、180点以上を取る必要があります。試験科目は大きく分けて2つです。行政書士の業務に関連する法律科目が244点、基礎知識科目が56点です。法律科目は1問4点で46問(記述式は1問20点)、基礎知識科目は1問4点で14問出題されます。法令科目は50%以上、基礎知識科目は40%以上の得点がなければ不合格です。
どちらかの科目が苦手でも、得意な科目でカバーできる可能性があります。試験はマークシート方式と記述式で行われ、試験時間は3時間です。時間内に、法律科目と基礎知識科目の合計60問を解答します。合格基準を満たすためには、全体の6割以上の正解が必要ですが、合格基準さえ満たしていれば、法令科目で得点できなかったところを基礎科目で補うということができます。
行政書士試験の日程と申し込み方法
行政書士試験は例年11月の第2日曜日に実施されます。申し込み期間は7月上旬~8月上旬までです。申し込み方法はインターネットか郵送のどちらかを選べます。受験手数料は10,400円で、全国の主要都市で受験できるので、自分に合った場所で受けましょう。
受験資格に年齢や学歴の制限はありませんが、申し込み時には以下の書類が必要です。
- 顔写真
- 本人確認書類のコピー(申込後に転居した場合)
試験当日は、合計で3時間程度かかります。受験票は試験の約2週間前に送られてくるので、忘れずに持参してください。合格発表は例年1月下旬です。申し込みは7月から1ヶ月ありますが、早く申込むと席順に影響したり希望会場での受験がしやすくなるので、早めに申し込みを済ませ、十分な準備期間を確保しましょう。
≫申込みの流れと早く申込むメリット
行政書士試験の合格に必要な勉強時間

行政書士試験の合格に必要な勉強時間は、個人差があります。計画的な学習時間の確保と効率的な学習方法が合格への近道です。ここでは一般的な勉強時間を書きます。ただ、私が推奨している勉強法だと勉強時間を2分の1から3分の1に短縮することが可能です。
≫私の実践した勉強法の全工程
合格に必要な勉強時間の目安
行政書士試験に合格するために必要な勉強時間は、平均的に1,000〜1,500時間程度です。フルタイムで働きながら勉強する場合、1年半〜2年の準備期間が必要になります。具体的な学習時間の目安は以下のとおりです。
- 1日2〜3時間
- 週10〜15時間
- 休日を利用した集中学習
勉強時間は個人の学習効率や基礎知識によって変動します。短期合格を目指す場合は、1日4〜5時間以上の学習が必要です。効果的な学習のためには、以下の点に注意しましょう。
- 過去問演習に200〜300時間程度を確保する
- 模擬試験の受験や答案練習にも時間を割く
- 休日を活用して集中的に勉強する
勉強時間を確保すると、合格に必要な知識と実践力を身に付けられます。
勉強時間を確保するコツ

勉強時間を確保することは、行政書士試験合格に向けて重要です。働きながら勉強する場合、時間の使い方を工夫する必要があります。以下の時間を有効活用してください。
- 通勤時間
- 昼休み
- 出勤前
- 就寝前
- 週末や休日
SNSや動画視聴の時間を制限すると、さらに勉強時間を確保できます。家事の効率化や外注をして家事代行サービスを利用することもおすすめです。勉強専用のスペースを確保すると、集中力が高まります。To-doリストを作成し、優先順位を付けて効率的に時間を使いましょう。
ポモドーロ・テクニックなどの時間管理法を活用すると、集中力を維持しながら効率的に勉強が可能です。さまざまな方法を組み合わせると、働きながらでも十分な勉強時間を確保できます。
≫勉強に集中できなかった私が実践した非常識な集中方法
効率的な学習スケジュールの立て方
効率的な学習スケジュールを立てることは、行政書士試験合格への近道です。長期的な目標と短期的な目標を設定し、自分の生活リズムに合わせて学習時間を確保することが大切です。1日の学習時間や科目配分、定期的な復習、模擬試験・過去問題の実施を計画的に行うと、効率良く勉強できます。
休憩時間も適切に設定して、集中力を維持しましょう。週単位や月単位でスケジュールを見直し、調整することも忘れないでください。進捗状況を記録すると、モチベーションを保てます。緊急時や予定変更に備えて、柔軟性を持たせることも重要です。
効率的な学習スケジュールを立てると、仕事と両立しながらも着実に試験対策を進められます。自分に合った方法を見つけて、継続的に取り組みましょう。
≫合格実績あり!合格者が実際に立てたスケジュール
行政書士試験の難易度に関するよくある質問
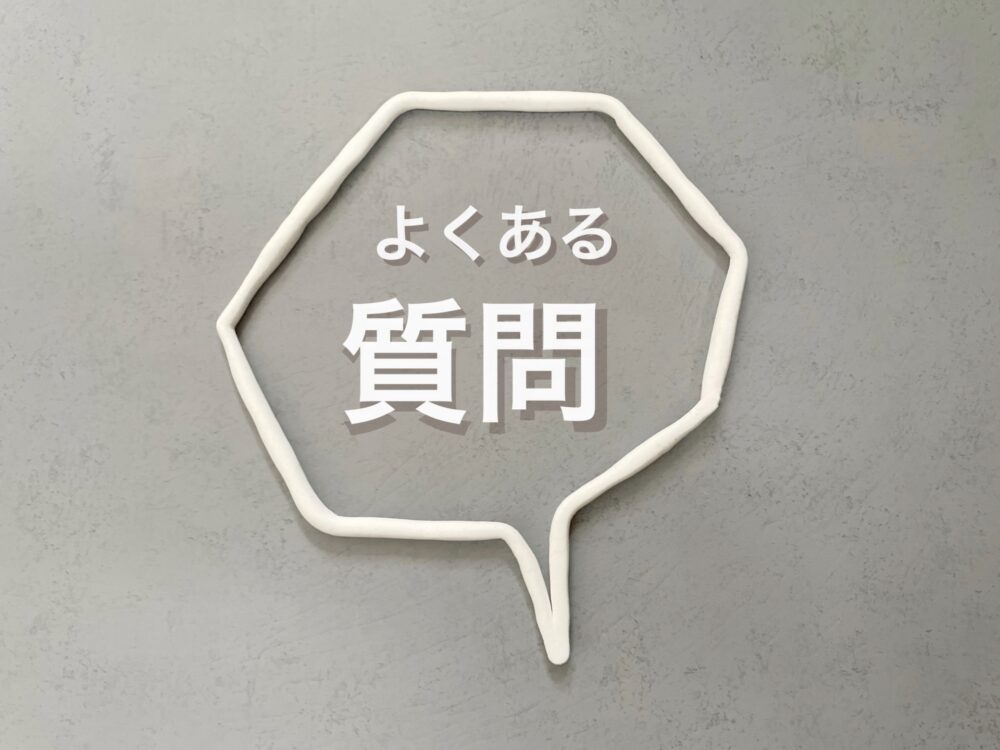
行政書士試験の難易度についての質問を以下にまとめました。
- 試験の難易度は上がっている?
- 独学でも合格できる?
- 受験資格に制限はある?
- 試験免除制度はある?
- 短期合格を目指すときのポイントは?
試験の難易度は上がっている?
行政書士試験の難易度は、年によって変動があるものの、大きくは上がっていません。近年の傾向としては、より実務に即した内容や応用力を問う問題が増えています。法改正や社会情勢の変化に伴い、出題範囲が広がり、新しい分野(情報公開法、個人情報保護法など)からの出題が増加している傾向です。
思考力を問う問題が増えていますが、問題の難易度自体は大きく変わっていません。合格ラインも年によって変動するため、一概に難易度が上がっているとは言えません。受験者数の増加により、相対的な競争率は高まっています。より深い理解と応用力が求められるようになっています。
独学でも合格できる?

独学でも行政書士試験に合格可能です。独学のメリットは、自分のペースで学習を進められる点です。多くの合格者が独学で試験に臨んでいるのが現状ですが、独学で合格するには高い自己管理能力と強い意志が必要になります。
基礎的な法律知識がない場合は、通信講座や通学講座を利用しましょう。独学で成功するためのポイントは以下のとおりです。
- 適切な参考書や問題集の選択
- オンライン学習ツールや動画講座の活用
- 定期的な模擬試験の受験
- 勉強仲間や先輩合格者とのコミュニティ参加
- 進捗管理と学習計画の定期的な見直し
苦手分野を克服したい場合は、専門家のアドバイスを受けることも検討してください。個人の学習スタイルや環境に合わせた方法を選択しましょう。
受験資格に制限はある?
行政書士試験の受験資格に厳しい制限はありません。年齢や学歴、国籍、職業に関係なく、誰でも受験できます。
行政書士試験は30~40代の合格者が一番多いためサラリーマンの方でも、現在の仕事を続けながら受験勉強に取り組めます。
試験免除制度はある?

行政書士試験には試験免除制度がありません。すべての受験者は、毎回全科目を受験する必要があります。他の資格保有者も免除されません。行政書士試験ではすべての受験者が平等に扱われます。合格を目指す場合は、すべての科目をしっかりと勉強することが大切です。
短期合格を目指すときのポイントは?
短期合格を目指すには、効率的な学習計画と集中的な取り組みが重要です。以下のポイントを押さえると、合格への近道を見つけられます。
- 過去問を徹底的に解く
- 重要科目に集中する
- 弱点分野を集中的に克服する
- 模擬試験を活用する
- 暗記ツールを活用する
ポイントを意識して学習を進めると、短期合格への道が開けます。
» 行政書士の資格は時間の無駄と言われる理由を解説!
まとめ

行政書士試験に合格するためには、効率的な学習計画と集中的な勉強が必要です。試験の難易度は中程度で、合格率は約10%前後です。働きながらの受験も十分可能ですが、600〜1,000時間程度の勉強時間が必要になります。独学での合格も可能ですが、適切な教材選びと学習方法が重要です。
受験資格に制限はないので、誰でもチャレンジできます。短期合格を目指すなら、過去問演習を中心とした集中的な学習が効果的です。行政書士試験は他の法律系資格と比較すると比較的取得しやすいです。しかし、合格するためには地道な努力と適切な学習戦略が欠かせません。
本記事で紹介した情報を参考に、自分に合った学習プランを立てて行政書士試験合格を目指してください。
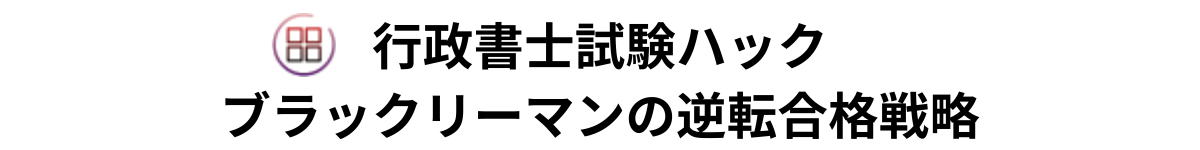



コメント