行政書士試験の勉強において、行政法の学習は必須です。行政法は学習範囲が広く、抽象的な表現も多いため、どこから手をつけるべきかわからず困っている人が多くいます。しかし、得点配分が高いため、行政法の学習を怠ると試験に合格できません。この記事では、行政書士試験の行政法の重要性や出題内容、学習法、ポイントを詳しく解説します。
記事を読めば、行政法の概要がわかり、効率良く学習を進められます。行政法を学ぶ際は、全体像の把握が重要です。ポイントを押さえながら、体系的に学びましょう。
» 行政書士試験の概要から勉強法、キャリアパスまで徹底解説
行政書士試験における行政法の重要性
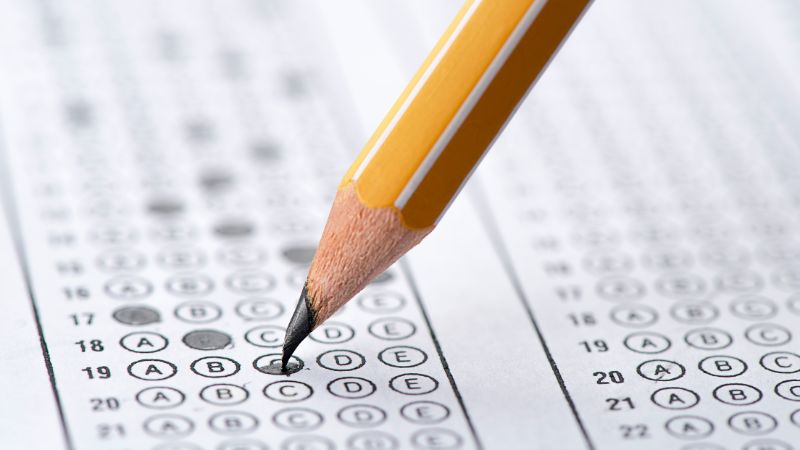
行政法は得点配分が多いため、優先して学ぶべき分野です。行政書士の業務に直結する知識を学ぶ必要があります。行政手続法や行政事件訴訟法、国家賠償法は試験で頻出するテーマです。確実に学んでおくと、高得点を狙えます。地方自治法や民法との関連性を理解すれば、応用問題にも対応できます。
効率的に学習を進めれば、行政書士の実務に役立つ知識の習得が可能です。行政法の学習は、試験合格と実務力の向上につながります。
行政書士試験の行政法の出題内容

行政書士試験の行政法では、以下の問題が出題されます。
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 地方自治法
行政法総論
行政法総論では、行政法の基本的な概念や原則の学習が可能です。行政立地の種類や行政行為の定義、行政裁量の意義について学べます。行政法総論は行政法全体の基礎であるため、正確に理解する必要があります。実務でも頻繁に登場するため、重点的に学習するのがおすすめです。
行政法総論は、具体例を交えて学ぶと効果的です。行政指導の事例を新聞記事で探し、行政法総論の性質や限界について考えましょう。法律による行政の原理や法治主義は、行政法の一般原則です。行政法を学ぶうえで重要な考え方のため、集中的に学習を進めてください。
行政手続法

行政手続法は行政運営の公正性と透明性を確保する法律で、試験頻出の分野です。以下4つの手続きを規定しています。
- 申請に対する処分
- 審査の基準や標準処理期間、理由の提示が定められています。
- 不利益処分
- 事前手続きとして、聴聞や弁明の機会が記載されている規定です。
- 行政指導
- 原則や方式、対象者が複数いる場合の手続きが定められています。
- 届出
- 行政への通知が到達した時点で、手続きが完了することが記載されている規定です。
行政手続法は、国の行政機関だけでなく地方公共団体にも準用されています。国会や裁判所、公正取引委員会では適用されない部分もあるため、注意が必要です。手続きの内容と法律との関係性を理解しましょう。実際の事例を交えて学習すれば、理解が深まります。
行政不服審査法
行政不服審査法は、行政庁の処分に不服がある場合の手続きを定めた法律です。再調査の請求や、審査請求の方法が規定されています。審査請求の期限は、処分を受けてから3か月以内です。審理には審理員による手続きが導入され、口頭での意見や物件の提出が認められています。
審査の流れは、以下のとおりです。
- 審理員が審理手続きをする
- 審査庁で審理員意見書を検討する
- 審査庁で裁決を行う
裁決には却下と棄却、認容の3種類があります。行政不服審査法では、教示制度により不服申立ての機会が保障されています。執行停止制度により、処分の効力を一時的に停止することも可能です。行政不服審査会への諮問手続きも規定されており、公平性の確保に努めています。
行政事件訴訟法

行政事件訴訟法は、国民と行政機関との紛争を解決するための法律です。行政事件訴訟法の学習では、訴訟の種類を把握する必要があります。取消訴訟は、訴訟要件や出訴期間に注目することが大切です。訴訟要件には処分性や原告適格があります。出訴期間は原則、処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内です。
執行停止制度や原告適格の拡大、判決の効力も重要なポイントです。訴訟の概念を理解し、詳細な事例に当てはめて考える必要があります。義務付け訴訟や差止め訴訟、確認訴訟の学習も必要です。新しい訴訟の要件や、審理の特徴も押さえましょう。
国家賠償法
国家賠償法は、公務員の違法行為による損害賠償を定めた法律です。国や公共団体の責任を明確にして、被害者の救済を目的としています。公務員個人ではなく、国や公共団体に賠償責任があります。
賠償責任が認められる条件は、以下のとおりです。
- 公権力を行使している
- 違法性がある
- 故意または過失がある
- 損害が発生している
国家賠償法の理解を深めるには、最高裁判例の学習が欠かせません。最高裁判例では、違法性の判断基準や因果関係の認定方法が示されています。行政書士試験では、国家賠償法に関する事例問題が多く出題されます。法律の条文だけでなく、実際の場面をイメージしながら学習を進めましょう。
地方自治法
地方自治法は、地方公共団体の組織と運営に関する基本法です。行政書士試験では、地方自治法の問題が多く出題されます。地方自治法の内容には、地方自治の具体化や都道府県と市町村の二層制、条例制定権などがあります。地方公共団体の事務や住民の権利も重要です。
地方自治法を学ぶには、基本的な概念や制度の理解が欠かせません。地方公共団体の組織構造や権限、住民の権利も重要なポイントです。詳細な事例や判例も同時に学習すると、より深く理解できます。
【分野別】行政書士試験の行政法の学習法

行政書士試験における行政法の学習法を以下の分野別に解説します。
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 国家賠償法
- 地方自治法
行政法総論
行政法総論は、行政法全体の土台となる知識を学ぶ分野です。行政法の基本概念や原則を理解できます。行政行為や行政計画といった用語の意味だけでなく、実務での適用例をイメージする必要があります。条文や判例を読み込み、行政法全体の仕組みを把握しましょう。
基本書やテキストで具体例を学ぶと理解が深まります。過去問を繰り返し解くことで、知識が定着します。過去問を通じて、試験の出題傾向に慣れることが大切です。
行政手続法

行政手続法では、行政機関が行う処分や手続きの基本ルールが定められています。行政書士試験では、頻繁に出題される問題です。以下のポイントを意識して、学習を進めてください。
- 通知の対象と範囲の理解を深める
- 意見公募手続の目的や実施方法を整理する
- 理由付記義務が適用される場面を確認する
条文と具体例を結びつけて学べば、知識が定着しやすくなります。過去問を分析して出題傾向を把握し、頻出するテーマを優先的に学習しましょう。
行政不服審査法
行政不服審査法は、行政に対する不服申立ての制度を扱う分野です。審査請求の手続きや期間、参加人制度などを理解する必要があります。裁判所における審理との違いを学べば、他の分野との関連性がわかります。制度全体の流れを図解にすると、複雑な手続きの整理が可能です。
過去問を通じて知識をアウトプットすれば、実践的な対応力が身に付きます。
行政事件訴訟法

行政事件訴訟法は、行政と市民の間で生じる紛争を取り扱う分野です。主要な判例を理解すれば、高得点が狙えます。学習のポイントは、以下のとおりです。
- 取消訴訟と義務付け訴訟の違いを整理する
- 出訴期間の起算点を理解する
- 訴訟要件の「法律上の利益」について理解する
主要な判例を中心に、背景となる事例を理解しましょう。判例集や条文集を活用すれば、より深く理解できます。
国家賠償法
国家賠償法は、国や地方公共団体の不法行為に対する損害賠償を規定する分野です。少ない条文で出題範囲が絞られるため、得点しやすいのが特徴です。国家賠償法では、公務員に賠償責任が生じる条件や、損害賠償請求の範囲を理解する必要があります。
過去問を通じて典型的な出題パターンを把握し、関連する判例を学びましょう。事例を考えながら学習を進めれば、試験本番での応用力が身に付きます。
地方自治法
地方自治法は、自治体の仕組みや権限を定めた分野です。条文数が多いため、効率良く学習を進める必要があります。地方自治の本旨や条例制定権、住民監査請求といったテーマは、試験で頻出します。
学習を進める際のポイントは、以下のとおりです。
- 条例と規則の違いを整理する
- 住民監査請求の手続きと範囲を確認する
- 地方議会の役割と権限を把握する
条文は具体例を交えて考えれば、記憶に定着しやすくなります。過去問を繰り返し解けば、より理解が深まります。
» 行政書士合格を目指す!試験の概要と効率的な勉強法
行政書士試験の行政法を学ぶときのポイント

行政書士試験の行政法を学ぶときのポイントは、以下のとおりです。
- 細かい部分にこだわりすぎない
- インプットとアウトプットのバランスを取る
- 体系的に学ぶ
- 模試を活用する
- 過去問を何度も解く
細かい部分にこだわりすぎない
行政法の学習では、細かい部分にこだわりすぎないことが大切です。基本的な概念や原則の理解に集中し、全体の流れを把握しましょう。行政法の学習で重要なポイントは、以下のとおりです。
- 重要な基本概念や原則を理解する
- 大きな流れや全体像を把握する
- 試験に頻出する主要な論点を把握する
細かい例外や特殊なケースは後回しにします。複雑な事例は、簡略化して考えるのがおすすめです。要点を覚えれば、効果的に学習を進められます。80%程度の理解で、次の内容に進むのも良い方法です。迷ったときは基礎を学び直すと、効率良く学習できます。
インプットとアウトプットのバランスを取る

インプットとアウトプットのバランスを取れば、効率的な学習が可能です。知識を吸収するだけでなく、実践的なアウトプットをする必要があります。学んだ内容を要約してノートにまとめたり、自分の言葉で説明したりするのがおすすめです。定期的に復習し、自己評価をつけることも大切です。
さまざまな方法でアウトプットすれば、知識が定着しやすくなります。理解できていない部分があれば、再度インプットを行いましょう。時間配分を考えつつ、インプットとアウトプットを繰り返すことが大切です。
» 勉強時間はどれくらい?行政書士になるための勉強法を解説!
体系的に学ぶ
行政法を効率良く学ぶには、体系的な学習が重要です。行政法の学習は、全体像を把握するところから始める必要があります。全体像を把握すれば、個々の法律や制度の関連性が理解できます。条文の構造と基本原則の学習は、法律を理解する際に重要です。
重要な判例や学説は試験で頻出するため、忘れずに整理しましょう。各分野の共通点と相違点を比較すれば、行政法全体の理解が深まります。
模試を活用する

模試を活用すれば自分の実力を客観的に把握できます。模試を受けるメリットは、以下のとおりです。
- 実際の試験と同じ形式で問題を解ける
- 自分の弱点や苦手分野を把握できる
- 試験での時間配分を把握できる
- 本番の緊張感を事前に体験できる
模試の結果を分析すれば、自分に合った学習計画を立てられます。弱点を重点的に学習したり、得意分野を伸ばしたりすると戦略的な学習が可能です。定期的に模試を受けると、学習の進捗も確認できます。模試の成績が向上すれば、モチベーション維持にもつながります。
複数の模試を比較して、幅広い問題を覚えられるのも大きなメリットです。さまざまな出題パターンに慣れれば、本番での対応力が身に付きます。
過去問を何度も解く
過去問を何度も解くことで、行政書士試験の出題傾向を把握できます。過去5年分の問題を繰り返し解けば、効率的な学習が可能です。間違えた問題は必ず復習しましょう。解説を見ながら復習すると、より理解が深まります。時間を計りながら問題を解けば、試験での時間配分を把握できます。
苦手分野を特定し、集中的に対策しましょう。問題文の読み方や解き方のコツもわかります。過去問を通じて、関連法令や判例も学習が可能です。隙間時間を活用すれば、働きながらでも学習できます。
行政書士試験の行政法を効率的に学ぶための時間管理術

行政法を効率的に学ぶための時間管理術は、以下のとおりです。
- 全体の学習スケジュールを設計する
- 1日の学習時間を割り振る
- ポモドーロ・テクニックを活用する
全体の学習スケジュールを設計する
試験日から逆算して、全体の学習スケジュールを設計することが大切です。行政法は範囲が広いため、無計画で始めると時間が不足します。基礎固めと応用学習、総復習の3段階に分けて学習を進めるのがおすすめです。最初の2〜3か月は基礎固めとして、各分野の基本的な理論や法律条文を理解しましょう。
中盤の3〜4か月は、応用学習を進めます。過去問や問題集を使って、実践力を身に付けます。試験前の1〜2か月は、総復習の期間です。過去問の反復練習や模試を通じて、試験対策を行います。段階的なスケジュールを作れば、効率的に学習できます。
1日の学習時間を割り振る

1日の学習時間をバランスよく配分すれば、効率的な学習が可能です。朝はインプットの時間として、行政法の条文や理論を学びましょう。朝の時間は、新しい知識を効率良く吸収できます。昼は解説動画やテキストを使いながら、細かい内容を学習してください。夜はアウトプットの時間として活用しましょう。
以下のような工夫をすると、効果的な学習が可能です。
- 詳細な学習テーマを決めて取り組む
- 理解できていない部分は解説書や参考書を見直す
- 疑問点を整理して効率的に解決する
問題集や過去問を解き、知識を実践的に使う練習をします。時間帯で学習内容を分ければ、効率よく知識を定着させられます。
» 行政書士試験にテキストはいらない?その理由とテキストを使わない勉強方法
ポモドーロ・テクニックを活用する
長時間集中できない場合は、ポモドーロ・テクニックの活用がおすすめです。ポモドーロ・テクニックは、25分の学習と5分の休憩を繰り返す方法です。学習と休憩のサイクルを繰り返せば、集中力を持続できます。学習を効率的に進めるためには、休憩時間の使い方も重要です。
休憩中はストレッチや深呼吸を行い、リフレッシュしましょう。リフレッシュを挟むと、次の学習サイクルで集中力の維持が可能です。ポモドーロ・テクニックを取り入れると、学習の質が高まります。
行政法の攻略が行政書士試験合格に近づく

行政法を対策すれば、行政書士試験の合格率が上がります。基本概念と重要ポイントを押さえて、主要分野をバランスよく学習することが大切です。模試や過去問で自分の弱点を把握し、対策を立てながら学習を進めましょう。継続的な学習と努力を重ねれば、行政書士試験合格を目指せます。
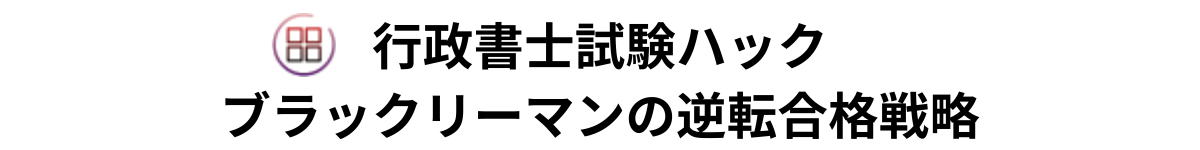
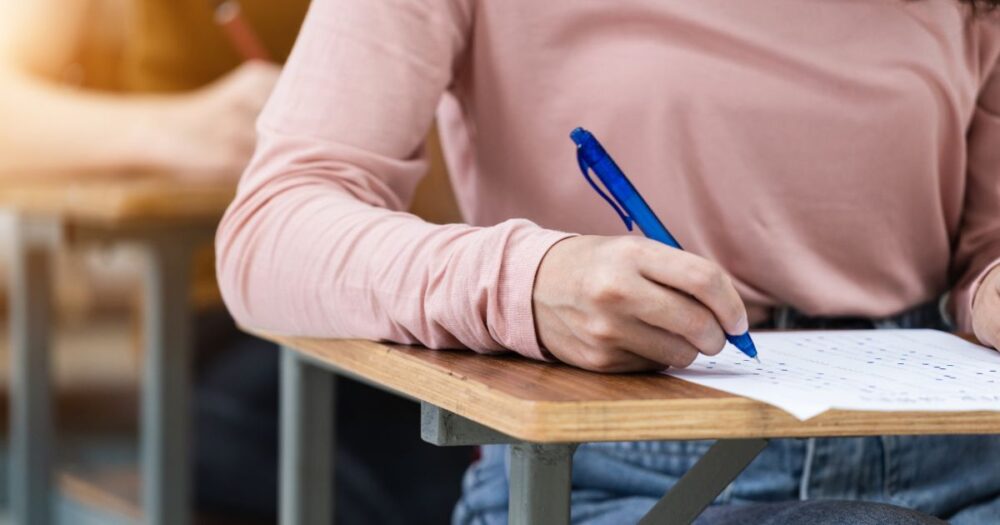

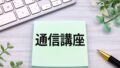
コメント