- 行政書士試験に合格したいけれど、勉強方法がわからない
- 仕事と両立しながら効率的に勉強する方法が知りたい
- 合格後のキャリアパスが不安で踏み出せない
行政書士は魅力的な資格ですが、勉強方法や試験内容、合格後のキャリアに不安を抱える人は多いです。この記事では、行政書士試験の試験内容から効率的な勉強方法、合格後のキャリアパスまで詳しく解説します。記事を読めば、働きながら勉強する方法や合格後のキャリアパスをイメージできます。
行政書士試験に合格するためには、計画的な勉強と効果的に学習する工夫が重要です。試験科目ごとの対策や過去問・模擬試験の活用方法を押さえ、合格への道を開きましょう。
行政書士試験の概要

行政書士試験は、総務省が毎年実施する国家資格試験です。行政書士として必要な知識や能力を評価するために行われます。合格率は10%程度と低く、十分な準備が必要です。
試験の目的
行政書士試験は、行政書士として必要な知識と能力を持つ人材を選抜するために行われています。行政書士試験に合格すると、行政書士資格が取得できます。試験の目的は、以下のとおりです。
- 行政手続きの円滑化
- 国民の利便性向上
- 専門知識を持つ人材確保
行政書士試験は、単なる資格試験ではありません。社会全体の利益に貢献できる人材を選ぶための重要な試験です。
受験資格
行政書士試験を受験するための要件は、以下のとおりです。
- 年齢 不問
- 国籍 不問
- 学歴 不問
- 性別 不問
- 職業 不問
- 受験回数制限 なし
働きながら勉強する30代のサラリーマンの方でも、十分に受験資格を満たせます。難関国家資格でありながら、誰でも受験できることが行政書士試験の魅力です。
試験日程・試験場所
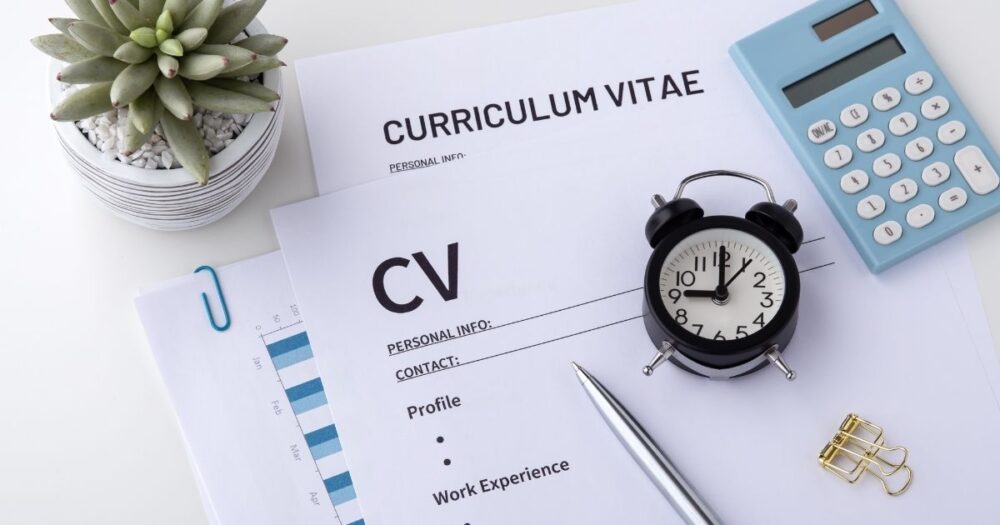
行政書士試験は、毎年11月の第2日曜日に実施されます。全国47都道府県の主要都市で開催され、受験者の居住地や都合に合わせて受験地の選択ができます。試験会場は10月下旬に郵送される受験票で通知されます。試験時間は午後1時〜4時までの3時間です。
障害のある方への配慮もあり、別室での受験などの特別な措置を受けられます。特例措置の詳細は行政書士試験研究センターで確認できます。また、台風や地震など特別な事情により試験が中止になった場合は受験料が返還されるため安心です。さまざまな状況に対応できるよう、準備が整えられています。
申し込み方法・受験手数料
行政書士試験の申し込み方法は、郵送とインターネットです。郵送の場合は受験願書を入手し、必要事項を記入して発送します。インターネットの場合は、指定のサイトから申し込みが可能です。受験手数料は10,400円で、郵送申し込みの場合は郵便局(ゆうちょ銀行)で払い込みます。インターネットではクレジットカード決済。コンビニ支払いが可能です。
申込期間は、例年7月下旬〜8月下旬までと指定されています。申し込みの際は、以下の3点に注意してください。
- 写真を用意する(縦4cm×横3cm)
- 受験願書の取り寄せ(郵送の場合)
- 期限内に手続きをする
行政書士試験の受験資格を得るために、しっかり準備しましょう。
行政書士試験の試験内容
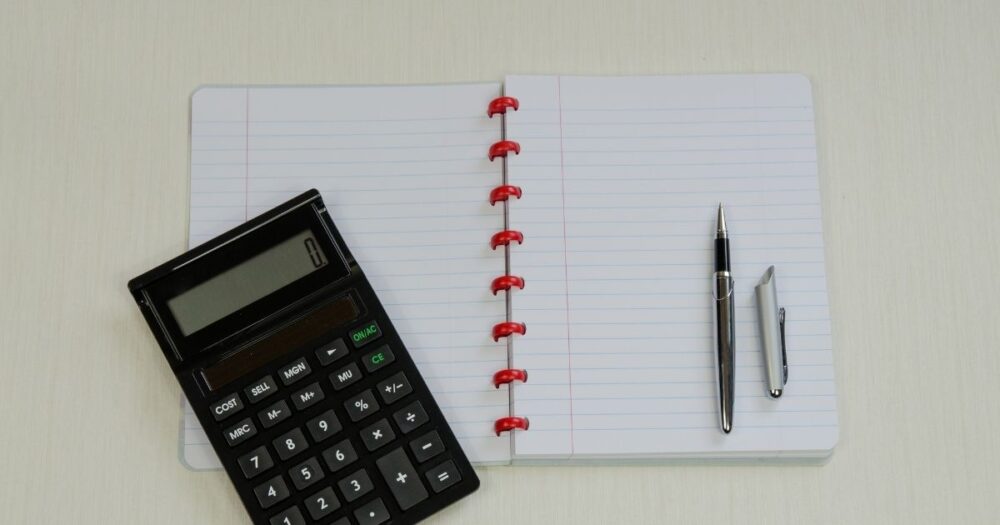
行政書士試験の試験内容について、試験科目・配点、出題形式を解説します。
試験科目・配点
行政書士試験の試験科目と配点は、以下の2科目に分かれています。
- 法令等科目:244点、46問
- 基礎知識等科目:56点、14問
試験の合計点は300点満点で、試験時間は3時間です。行政書士試験は幅広い知識と、応用力が求められる試験です。各科目の配点を意識しながら、バランスの取れた学習計画を立ててください。
出題形式
行政書士試験の出題形式は、選択式(択一式と多肢選択式)と記述式の2種類があります。択一式は54問で構成されており、多岐選択式は3問、記述式が3問あります。択一式問題では、5つの選択肢から正しい答えを1つ選び、多肢選択式では、20個の選択肢から法文や条文を穴埋めする形式となっています。記述式問題では空欄に適切な言葉を入れて40文字程度で文章を完成させます。
どの形式も、幅広い法律の知識が求められる点が特徴です。出題形式を意識して普段から勉強すると、本番の試験でも落ち着いて解答できます。試験対策では、過去問題を活用して実際の出題形式に慣れておきましょう。
行政書士試験の合格基準
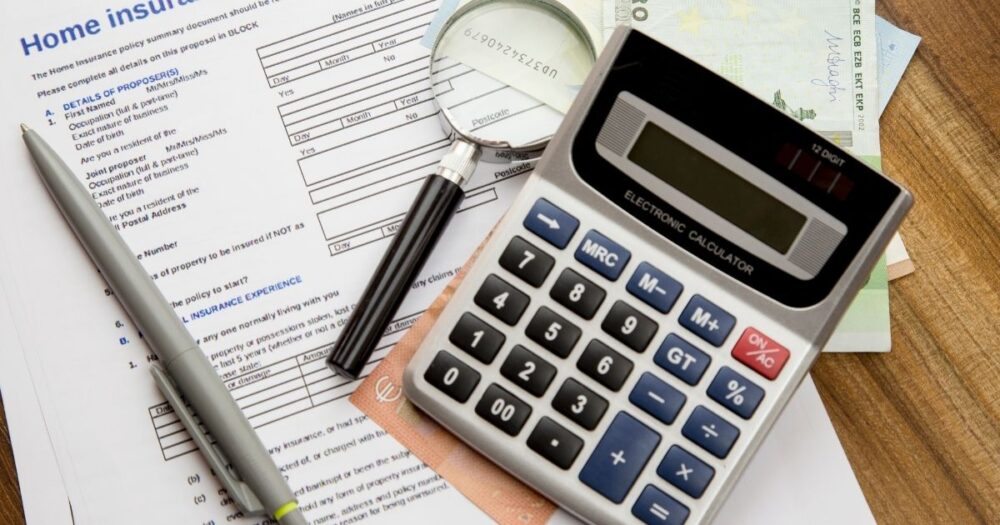
行政書士試験の合格基準は、総合得点60%以上であるとともに、法令科目で50%以上、基礎知識科目で40%の得点が必要です。足切り制度があるため、一定点数未満は不合格とされます。合格率は低く、難易度の高い試験と言えます。
合格ライン
行政書士試験の合格基準は、以下の3つが条件です。
- 総合:180点以上の得点(総合得点60%以上)
- 法令科目:122点以上の得点(法令科目の50%以上)
- 基礎知識等科目:24点以上の得点(基礎知識の40%以上)
過去5年間の合格平均点は190点前後で推移しています。年度によって多少の変動はあるものの、合格者の平均点は190点程度です。合格を目指すためには、法令科目を重点的に学習し、過去問や模擬試験にも取り組みましょう。
足切り制度

足切り制度は、一定の点数に達しない科目がある場合に、総得点に関わらず不合格とされる仕組みです。足切り点は、法令等科目が50%未満、一般知識等科目が40%未満と設定されています。例外として2014年に補正措置として合格点が180点から166点に引き下げられました。今後試験難易度に合わせて合格点が変わるかは不明です。総合得点・法令科目・基礎知識どれか一つでも足切り点を下回ると不合格になることは覚えておきましょう。
行政書士試験の合格基準を満たすためには、バランスの取れた学習が重要です。苦手科目の底上げに力を入れましょう。足切り制度を意識して勉強すれば、効率的に試験対策を進められます。苦手科目を克服し、全科目でしっかり点数を取れるよう努力しましょう。
合格率の推移
行政書士試験の合格率は、以下のとおり10〜15%の範囲で推移し、毎年4〜5,000人が合格しています。
- 2023年度:14.0%
- 2022年度:12.1%
- 2021年度:11.2%
- 2020年度:10.7%
- 2019年度:11.5%
- 2018年度:12.7%
合格率は年度によって変動はありますが、行政書士試験の難易度は高いので合格率は10%と低いです。しかし、合格率が低いからといってあきらめる必要はありません。しっかりと対策を立てて勉強すれば、合格できる可能性は十分にあります。
» 行政書士試験の難易度や他の資格と徹底比較!
【科目別】行政書士試験の対策方法
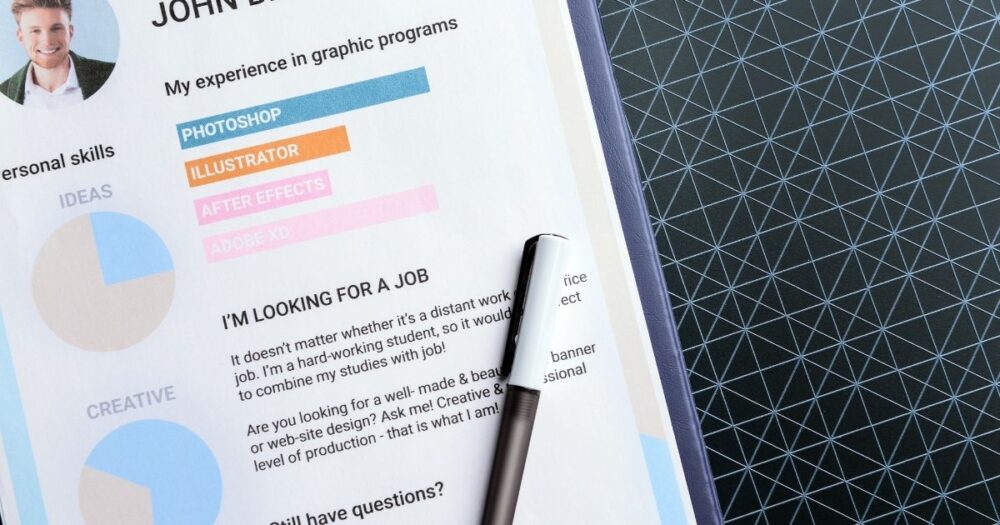
行政書士試験は、法令等科目と基礎知識等科目の2つです。各科目の特性に合わせた対策と過去問を解いて、実践力を付けましょう。重要度を把握し、効率的な学習時間の配分と弱点の強化が必要です。
» 行政書士試験の科目・試験免除制度について解説!
法令等科目
法令等科目は、行政書士試験の中心となる重要な分野です。法令等科目では、憲法や行政法、民法、商法などの基本的な法律知識が問われます。憲法では基本的人権や統治機構、地方自治に関する知識が必要です。行政法では行政組織法や行政作用法、行政救済法などの理解が求められます。
民法は総則や物権、債権、親族、相続に関する基礎知識を学びます。商法では会社法や商行為法などの理解が必要です。基礎法学として法令用語や法令解釈、法令構造について学びましょう。情報公開法や個人情報保護法、行政手続法なども重要な学習項目です。
複数の法律を効率的に学ぶためには、体系的な理解が欠かせません。法律の基本的な考え方や構造を押さえたうえで、具体的な条文や判例を学びましょう。
基礎知識等科目
基礎知識等科目は、幅広い分野の知識が問われる科目です。政治や経済、社会、歴史、文化、地理など、さまざまな分野の基礎的な知識が求められます。基礎知識科目の対策法は、以下のとおりです。
- 新聞やニュースをチェックする
- 一般常識問題集を活用する
- 過去問の繰り返しを行う
基礎的な知識を着実に積み重ねていくと、合格につながります。
行政書士試験の効率的な勉強方法

行政書士試験合格のための効率的な勉強方法は、以下のとおりです。
- 勉強スケジュールの組み方
- 過去問の活用方法
- 模擬試験の活用方法
- 直前対策のポイント
上記の方法を組み合わせると、効率的に試験対策を進められます。
勉強スケジュールの組み方
効率的な勉強スケジュールを組み立てると、限られた時間を最大限に活用できます。1年間の大まかなスケジュールを立てれば、全体の流れの把握が可能です。週単位や月単位の具体的な計画を作成してください。平日と休日で異なる学習時間を設定することもポイントです。
以下の点にも注意して、時間を割り当てましょう。
- 弱点科目
- 定期的な復習
- 模擬試験や過去問演習
通勤時間などの隙間時間の活用もおすすめです。睡眠や休息の時間も確保してください。進捗状況に応じて柔軟な調整が大切です。目標達成したときの小さな報酬を設定すると、モチベーション維持に役立ちます。スケジュール管理には、アプリやカレンダーを活用しましょう。
過去問の活用方法
過去問の活用は、行政書士試験に合格するための近道です。過去問を繰り返し解きましょう。間違えた問題は重点的に復習してください。解説をじっくり読んで理解を深めると、同じ間違いを繰り返さなくなります。時間を計って解く方法もおすすめです。本番の時間感覚をつかめ、出題傾向や頻出分野の分析もしやすくなります。
類似問題を探して、パターンを習得する工夫も効果的です。正解した問題も再度チェックして、確実に理解を深めましょう。過去問を暗記するのではなく、考え方を学ぶことが重要です。過去問は、最低でも過去5年分は解いてください。
解答を見ずに自分で考える時間を設けると、問題文の読み方や解き方のコツをつかめます。過去問を通じて法令の条文に慣れれば、本番でも落ち着いて問題に取り組めます。効果的に過去問を活用して、行政書士試験合格を目指しましょう。
模擬試験の活用方法

模擬試験は本番と同じ形式・時間で解くと、実際の試験の雰囲気に慣れることが可能です。模擬試験の結果から弱点科目や苦手分野を把握し、効率的な学習計画を立てましょう。時間配分の練習も重要です。各科目にかけるべき時間を実践的に学んでください。
効果的に模擬試験を活用するために、以下の点にも注意しましょう。
- 緊張感のある環境で解く
- 学習計画の見直し
- 他の受験者との成績を比較する
解答後は詳細な解説をしっかり確認し、間違えた問題は丁寧に復習することが大切です。得点率の推移を確認すると、自分の進捗状況を把握できます。伸び悩んでいる分野があれば、学習方法の見直しにつながります。複数の模擬試験を受ければ、出題傾向の把握が可能です。
直前対策のポイント
直前対策のポイントは、以下のとおりです。
- 重要論点の最終確認
- 過去問の見直し
- 時間配分の練習
- 苦手分野の集中復習
- 暗記事項の最終チェック
- 解答テクニックの確認
- メンタル面の調整
- 試験当日の持ち物準備
- 体調管理と睡眠の確保
- 試験会場の下見
ポイントを押さえると、試験本番で実力を発揮できます。
行政書士試験受験後のキャリアパス

行政書士試験に合格した後は、多様なキャリアパスが開かれます。許認可申請の代行や契約書作成などの幅広い業務があり、個人開業や法人就職、副業など働き方も選択が可能です。専門分野に特化すれば、高収入も目指せます。
行政書士の業務内容
行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成や各種許認可申請の代行です。一般の方にとって複雑で難しい手続きを助ける役割を担います。業務内容は、以下のとおりです。
- 契約書や遺言書の作成
- 法人設立手続きの支援
- 外国人の在留資格申請支援
- 建設業許可申請の支援
- 相続・遺言に関する手続き支援
行政書士は、個人や企業の権利を守り、円滑な社会活動を支える魅力的な職業です。専門知識を生かして依頼者の立場に立ちながら、適切な助言や手続きの代行を担います。社会に貢献できる仕事であり、やりがいを感じられる職業です。
» 行政書士資格取得の試験の概要から仕事内容まで幅広く解説!
行政書士の働く場所

行政書士の働く場所は、多岐にわたります。就業先は、以下のとおりです。
- 弁護士事務所
- 税理士事務所などの他の士業事務所
- 不動産会社
- 建設会社
- 自動車販売会社
- NPO法人
- コンサルティング会社
- 金融機関
社会保険労務士事務所や特許事務所、会計事務所などでも行政書士の資格を持つ人材が求められています。起業支援センターなど、新規事業の立ち上げを支援する仕事もおすすめです。行政書士の資格を持つと、さまざまな分野で活躍できます。自分の興味や得意分野に合わせて、働く場所を選びましょう。
» 行政書士の資格は時間の無駄と言われる理由を解説!
キャリアアップの方法
行政書士として成功するためには、スキルアップと専門性の向上が基本です。継続的な学習と研修への参加も欠かせません。法改正や新しい技術に迅速に対応し専門分野を確立すると、他の行政書士との差別化が図れます。ネットワークの構築と人脈の拡大も重要です。業界団体や協会に積極的に参加しましょう。
多様な案件を受託し、経験を積むことも重要です。マーケティングスキルと顧客サービスの質を向上させれば、クライアントの獲得と維持につながります。独立開業を目指す場合は、経営スキルの習得も必要です。他の資格取得により、複合的なサービスを提供できます。
オンラインプレゼンスを確立・強化し、認知度を高めることもおすすめです。講師やセミナー講演、執筆活動、メディア出演などを通じて、自身のブランディングをしましょう。地域や社会貢献活動への参加も、信頼性の向上につながります。自分に合った方法で着実にキャリアアップすることが大切です。
行政書士試験合格には効率的なスケジュールが必須

行政書士試験は、努力と計画的な準備があれば十分に合格できます。試験の概要や内容を理解し、効果的な勉強方法を実践しましょう。働きながらの受験は大変ですが、効率的なスケジュールを立てることで両立できます。
合格後はさまざまなキャリアが開けるので、行政書士としての新しい人生に向けて、一歩ずつ着実に前進してください。
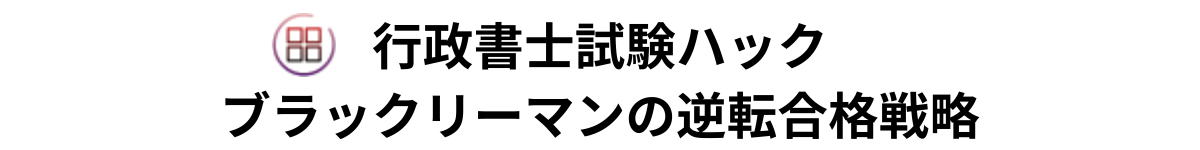



コメント