行政書士と司法書士の違いがわからず悩んでいませんか?特に働きながら早期独立を目指す30代にとっては、どちらの資格を選ぶかは将来を左右する大きな選択です。
この記事では、行政書士と司法書士の違いについて解説します。行政書士と司法書士の業務内容や試験の難易度、年収、将来性、向いている人の特徴なども紹介しています。ダブルライセンスのメリットや資格取得の流れにも触れているので、どちらを目指すか迷っている人にとって参考になる内容です。
行政書士と司法書士では、活躍できる業務範囲や試験の難易度が異なります。働きながら早期合格を目指し、独立開業するには、目標や学習スタイルに合った資格を選ぶことが成功への近道です。
» 行政書士になるための3つのルートを詳しく解説!
行政書士と司法書士の業務の違い

行政書士と司法書士は、いずれも法律の専門家ですが、業務には法律上の制限があります。行政書士と司法書士それぞれの業務と制限について解説します。
行政書士の業務と制限
行政書士の主な業務は、役所に提出する書類の作成や相談の対応です。ただし行政書士の業務には制限があり、以下のように対応できる業務とできない業務があります。
| 分類 | 行政書士にできる業務 | 行政書士にできない業務 |
| 書類作成 | 官公署への提出書類の作成や契約書、遺言書、内容証明、定款・議事録など事実証明書類の作成 | 訴状や答弁書など、裁判所への提出書類の作成 |
| 相談・助言 | 書類作成に関する相談や手続きのアドバイス | 紛争に関する法的助言、当事者間の代理交渉 |
| 代理業務 | 書類の役所提出代理(本人に代わって申請・提出) | 登記申請の代理(司法書士の業務)や、税務申告の代理(税理士の業務) |
| 特定業務 | 不服申立て手続きの代理(特定行政書士のみ) | 訴訟代理や調停、示談交渉など裁判手続き全般 |
行政書士の業務は「行政書士法」で定められており、他の専門家と業務が重ならないよう、明確に役割が分かれています。
» 行政書士の仕事内容とは?業務内容から必要なスキルまで解説
司法書士の業務と制限
司法書士は、法律相談や代理業務などを専門的に行う法律のプロです。司法書士が対応できる業務と対応できない業務は以下のとおりです。
| 分類 | 司法書士にできる業務 | 司法書士にできない業務 |
| 登記関連 | 不動産登記商業・法人登記 | 登記以外の官公署への申請業務(行政書士の業務) |
| 書類作成 | 裁判所・検察庁・法務局への書類作成供託書類の作成 | 税務書類の作成(税理士の業務)、許認可申請書類の作成(行政書士の業務) |
| 代理業務 | 簡易裁判所での代理(認定司法書士)、供託手続きの代理(請求額が140万円以下) | 地方裁判所以上の訴訟代理、高額な民事事件(請求額が140万円超)の代理 |
| 相談・支援 | 債務整理成年後見・財産管理の支援 | 刑事事件の弁護(弁護士の業務)、行政書士・税理士の専門分野 |
司法書士の業務範囲は法律で厳格に定められており、他士業の専門分野に関わる業務は原則行えません。
行政書士と司法書士の試験の違い
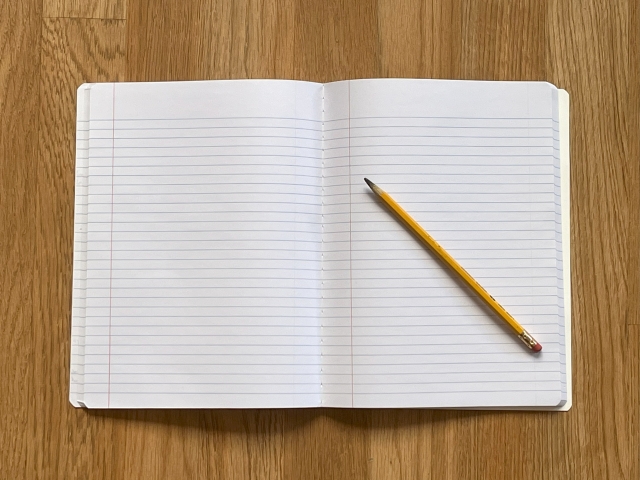
行政書士と司法書士は担当業務が異なるため、試験で問われる知識や合格条件も違います。行政書士試験と司法書士試験の違いについて解説します。
行政書士試験
行政書士試験は、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できる国家資格ですが、合格率は10%前後と低く難易度の高い試験です。
行政書士試験は年に1回、11月に実施されます。行政書士試験は「法令等科目」と「基礎知識等科目」の2つの分野から出題され、解答は主にマークシート方式です。法令等科目は配点が高く、記述式問題も含まれています。
行政書士試験に合格するには法令等科目で50%以上、基礎知識等科目で40%以上の得点が必要です。さらに、全体の得点が60%を超えていなければなりません。1つでも基準に達していない場合は不合格になります。
働きながら行政書士試験の合格を目指す場合は、学習時間として800〜1,000時間が目安です。行政書士試験の記述式問題は、過去問を繰り返し解くことで実力が身に付きます。
» 行政書士試験の概要から勉強法、キャリアパスまで徹底解説
» 行政書士試験の難易度や他の資格と徹底比較!
司法書士試験
司法書士試験は法務省が所管する国家資格で、出題範囲が広く、合格率3〜5%の難関試験です。司法書士試験は年に1回実施され、受験には学歴や年齢の制限がありません。筆記試験に合格した人のみが、口述試験に進めます。司法書士試験の詳しい内容は以下のとおりです。
| 試験区分 | 出題形式 | 内容例 |
| 午前の部 | 択一式 | 憲法・民法など |
| 午後の部 | 択一式 | 会社法など |
| 記述式問題 | 記述式 | 不動産登記など |
司法書士試験では各試験区分(午前・午後・記述)の基準点だけでなく、筆記全体の得点も合格基準に達する必要があります。司法書士試験の基準点は、毎年の試験の難易度や受験者の得点状況に応じて変動します。
行政書士と司法書士の年収の違い

行政書士と司法書士は専門性の高い資格ですが、平均年収は司法書士の方が高い傾向にあります。行政書士の年収と司法書士の年収について解説します。
行政書士の年収
行政書士の平均年収は500〜600万円程度ですが、働き方によって大きく変わります。自分で事務所を開くか他の事務所に勤務するかによって、収入の幅や安定性が異なるためです。
開業行政書士の年収は、300万円未満〜1,000万円を超える人までさまざまです。行政書士として得意な分野や営業力、働き方、専門分野、経験によって収入は大きく変動します。開業直後は依頼が少なく、年収が200〜300万円ほどになる場合もあります。
行政書士事務所などで働く「勤務行政書士」の場合、年収は300〜500万円程度で安定した収入を得やすいです。高収入を目指すには、実績や経験に加え、得意分野を持つと効果的です。たとえば、許認可業務や外国人ビザ、相続手続きなどに精通していると依頼が増えやすく、収入アップにつながります。
司法書士の年収
司法書士の平均年収は600〜800万円程度ですが、働き方や経験、専門分野、地域などによって収入に大きな差があります。開業する場合は、営業力や経営手腕によって年収1,000万円を超える場合があります。司法書士事務所に勤務する場合、初年度の年収は300〜500万円程度です。
都市部の事務所や会社の法務・国際案件を扱う事務所で働く場合、高収入が期待できます。収入アップを目指すなら、以下のような分野に特化すると効果的です。
- 相続手続き
- 事業承継手続き
- M&A法務
- 信託業務
新規顧客の獲得や相談者との信頼関係を築く力も重要な要素です。
行政書士と司法書士の将来性の違い

行政書士と司法書士は将来性のある職業ですが、それぞれに違いがあります。行政書士の将来性と司法書士の将来性について解説します。
行政書士の将来性
AIの進化により行政書士の仕事が減ると言われていますが、変化に柔軟に対応し、専門性を高めれば活躍の場を広げられます。行政書士の仕事は、コミュニケーション能力や複雑な状況判断が求められるため、人の力が不可欠です。
ドローンや民泊、外国人労働者への許認可、高齢化に伴う相続、成年後見の支援などは行政書士の需要が増え続けています。中小企業の経営や事業承継のサポートも行政書士が活躍できる場です。
IT化やオンライン申請に対応し情報発信や営業力を高めることも、行政書士として継続的に活躍するために重要です。特定分野に特化し、弁護士など他の専門家と連携すると幅広いニーズに対応でき、行政書士として信頼される存在になれます。
司法書士の将来性
司法書士は、社会の変化に対応しながら活躍の場を広げられる将来性のある仕事です。具体的には、以下の分野で司法書士の専門性が求められています。
| 活躍が期待される分野 | 業務内容の例 |
| 高齢化社会対応 | 相続手続き、遺言書作成サポート、成年後見制度 |
| 不動産関連 | 売買や相続に伴う名義変更手続き |
| 企業法務 | 会社設立、役員変更、組織再編の登記 |
| 裁判業務 | 簡易裁判所における代理業務(認定司法書士) |
| 新法・制度対応 | 空き家・所有者不明土地の処理など |
| 専門分野への特化 | 信託、事業承継、国際法務など |
| 地域貢献 | 司法書士が不足する地域での活動 |
高齢化や新制度の導入、デジタル化の進展などにより、司法書士が必要とされる場面は今後さらに重要になります。
» 行政書士資格のメリットから試験概要・仕事内容まで幅広く解説
行政書士と司法書士に向いている人の違い

行政書士と司法書士は仕事内容が異なるため適性も違います。行政書士に向いている人の特徴と、司法書士に向いている人の特徴を解説します。
行政書士に向いている人の特徴
行政書士に向いている人には、以下の特徴があります。
- 細かい作業を苦にせず進められる
- 人の役に立つことに喜びを感じる
- コミュニケーション能力がある
- 自分で事業を育てたい意欲がある
- 法律や制度に興味を持ち、学ぶことを楽しめる
- 一度決めた目標に向かって努力を続けられる
行政書士に向いている特徴に多く当てはまる人は、行政書士としてやりがいを感じながら成長できます。
» 行政書士に向いている人・向いていない人の特徴
司法書士に向いている人の特徴
司法書士に向いている人は正確さと責任感があり、細かい作業を丁寧にこなせるタイプです。司法書士は登記や書類作成などミスが許されない業務が多いため、慎重に作業を進める力が求められます。
司法書士には、法律に関心を持ち継続的に知識を深めようとする姿勢も必要です。依頼者の悩みや要望を正確に把握するには傾聴力が欠かせません。複雑な法律の内容を相手に合わせてわかりやすく伝える力も司法書士に不可欠です。
司法書士として開業を目指す場合は、経営感覚や営業力、柔軟な対応力も求められます。信頼関係を大切にし、地道に努力を重ねられる人は、司法書士として長く活躍できる素質があります。
行政書士と司法書士のダブルライセンス

行政書士と司法書士のダブルライセンスは、専門家としての活動範囲を拡大し、顧客へのワンストップサポートを可能にします。ダブルライセンスに関して、特に押さえておきたい以下の2点について解説します。
- ダブルライセンスのメリット
- ダブルライセンスの取得方法
ダブルライセンスのメリット
行政書士と司法書士の資格を両方持つ(ダブルライセンス)と、仕事の幅が広がり、収入アップや信頼につながります。分野ごとの専門知識も深まるので、複雑な案件にも自信を持って取り組めるようになります。依頼者の悩みをまとめてサポートできる点がダブルライセンス取得の大きな強みです。
ダブルライセンスがあれば業務効率が向上するうえ、独立後の安定経営にもつながります。ダブルライセンスがあると顧客の期待にも応えやすくなるため、経営の安定化も期待できます。
ダブルライセンスの取得方法
行政書士と司法書士は異なる国家資格で、ダブルライセンスの取得には、段階的で効率的な学習の積み重ねが不可欠です。行政書士試験で身に付けた法律知識(特に民法)は、司法書士試験でも生かせます。
ダブルライセンスを目指すなら、行政書士から始めると効率的です。最初に行政書士試験に合格して名簿への登録(※)を済ませ、次に司法書士試験の学習に進みましょう。ダブルライセンスを維持するために、各登録条件や年会費、研修義務なども把握しておく必要があります。
司法書士資格を先に取得した場合、行政書士試験を受けずに行政書士として登録できる制度もあります。ただし、司法書士は行政書士よりも高度な知識が必要で、実務経験を求められる場合もあるため難易度は高めです。
※ 名簿への登録とは、各都道府県の行政書士会を通じて、正式に行政書士として業務を行うための登録手続きのことです。
行政書士と司法書士の違いに関するよくある質問

行政書士と司法書士の違いに関する、よくある質問をまとめました。ダブルライセンスの取得や、それぞれの資格を検討している人は、参考にしてください。
行政書士と司法書士で重複している業務は?
行政書士と司法書士はいずれも、顧客の権利や財産を守ることが目的です。共通する主な業務には以下のものがあり、行政書士・司法書士どちらでも対応できます。
- 会社設立の書類作成
- 遺言書や遺産分割協議書の作成
- 内容証明郵便・契約書の作成
- 成年後見制度の手続き書類の作成
司法書士から行政書士になれる?

司法書士の資格があれば、行政書士法第2条の2第8号により、試験を受けずに行政書士になることが認められています。ただし、実際に行政書士として活動するには、日本行政書士会連合会への登録が必要です。日本行政書士会連合会に登録するには、司法書士として有効に登録されていることが前提です。
申請者は必要書類を提出し、登録料を納付する必要があります。日本行政書士会連合会の登録審査では、司法書士としての実務経験が2年以上あるかを確認される場合があります。司法書士の実務経験が必要かどうかは、各地域の行政書士会の判断に委ねられており、確認が必要です。
行政書士試験と司法書士試験はどちらが難しい?
司法書士試験は法律系資格の中でも特に難関とされ、行政書士試験よりも難易度が高い資格です。司法書士試験の難易度が高い理由は、行政書士試験と比べて以下の点でハードルが高いためです。
| 比較項目 | 行政書士試験 | 司法書士試験 |
| 学習時間 | 約600〜1,000時間 | 3,000時間以上 |
| 合格率 | 約10% | 約3〜5% |
| 試験科目 | 法令(憲法・民法・行政法など) | 民法・不動産登記法・商業登記法など専門的 |
| 試験形式 | マーク式+記述式 | マーク式+記述式+口述試験 |
働きながら資格を早く取得して開業を目指すなら、司法書士試験より行政書士試験のほうが現実的です。
ダブルライセンスは本当に必要?
ダブルライセンスは、最初から無理に目指す必要はありません。働きながら行政書士と司法書士の両方を取得することは負担が大きく、行政書士の資格だけでも十分に活躍の場があります。
まずは行政書士試験に合格し、開業して経験を重ねることに集中してください。行政書士として働く中で必要性を感じたら、司法書士の資格取得を検討しましょう。行政書士として専門性を高めれば仕事の幅が広がり、収入の安定にもつながります。
ダブルライセンスを目指すかどうかは、自分の将来像や働き方に合わせて考えましょう。
キャリアプランに合わせて資格取得を考えよう
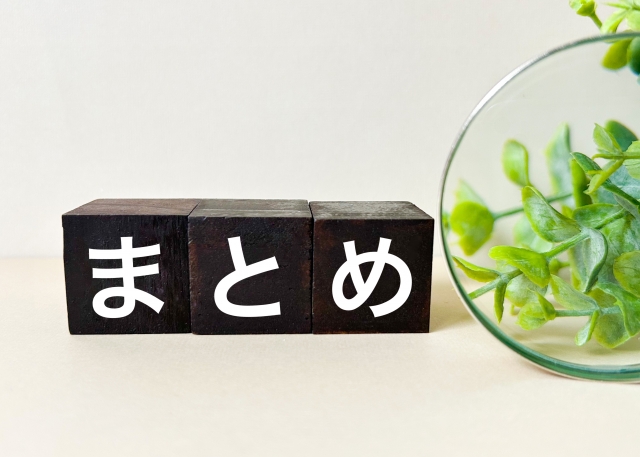
行政書士と司法書士の主な違いは、取り扱う業務の範囲と試験の難易度にあります。行政書士は行政書士法で定められた業務を行い、比較的短期間の学習で合格を目指しやすい点が特長です。司法書士は登記や簡易裁判所での代理業務など、より専門性の高い業務を担い、試験の難易度も高くなっています。
行政書士と司法書士のどちらを目指すかは、目標や状況に合わせて選びましょう。早く独立したい30代の会社員には行政書士の方が現実的です。行政書士試験は比較的難易度が低く、働きながらでも合格を目指しやすいためです。
司法書士は高収入も期待できますが、長期間の学習が求められます。ダブルライセンスを目指すなら、まず行政書士に合格して実務経験を積みながら司法書士を目指す流れが効率的です。
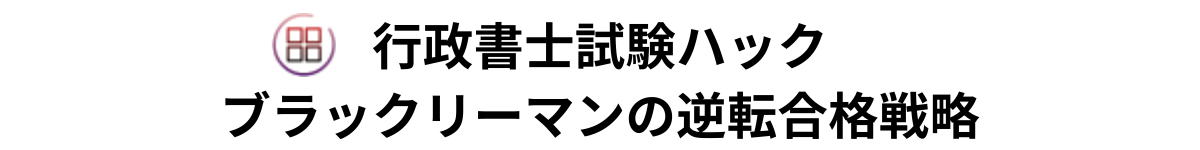



コメント